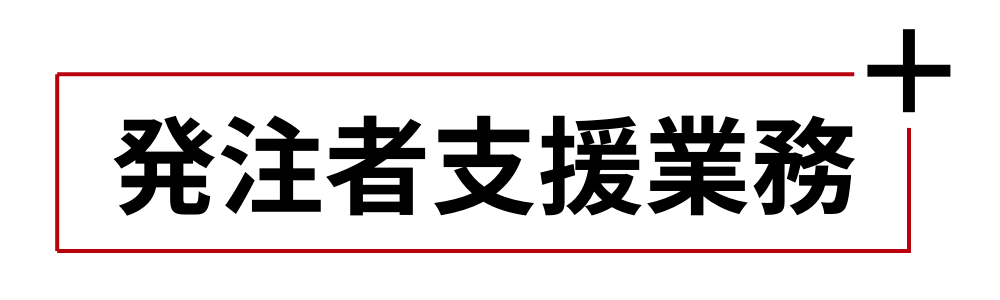「今の現場が終わった後、次はどこの現場になるのだろう?」
「会社の利益がどうやって決まっているのか、入札の仕組みを詳しく知りたい」
「将来のために、積算や見積もりの知識も身につけておきたい」
現場で汗を流す施工管理技士にとって、仕事の入り口である「入札」は少し遠い存在に感じるかもしれません。しかし、公共工事がどのように発注され、どのようなルールで事業者が決まるのかを理解することは、建設業で働く上で非常に重要です。
本記事では、2025年の最新動向も踏まえ、公共工事入札の流れや基礎知識を実務者向けに解説します。また、記事の後半では入札の裏側で重要な役割を果たす「発注者支援業務」についても触れていきます。
公共工事入札の基本概念

公共工事とは、国や地方自治体などの公的機関が発注する道路、橋梁、河川、庁舎などの建設工事のことです。これらは国民の税金を原資としているため、業者選定においては「透明性」「公正性」「競争性」が厳格に求められます。
入札とは、発注者が工事の内容や条件を提示し、参加を希望する建設業者が「いくらで請け負えるか(入札金額)」や「どのような技術で施工するか(技術提案)」を提示するプロセスのことです。
ここで重要なのが、発注者側があらかじめ算出しておく「予定価格」です。この予定価格を入念に計算し、適正な調達を行うために膨大な業務を支えているのが、実は「発注者支援業務」の技術者たちです。
公共工事入札に参加するための準備
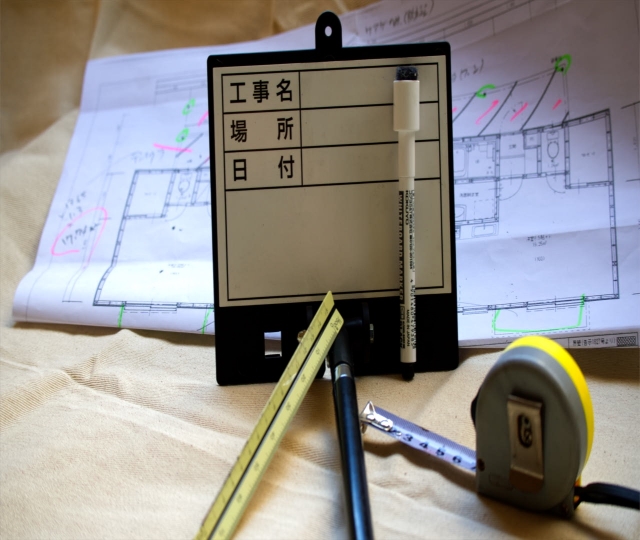
建設会社がいきなり入札に参加できるわけではありません。事前に以下の手続きを経て、参加資格(要件)を満たす必要があります。
1. 建設業許可の取得
まず大前提として、建設業法に基づく建設業許可を有することが必須です。業種ごとに許可を受け、適正に事業を運営していることが求められます。
2. 経営事項審査(経審)の受審
会社の経営状況、技術力、社会性などを数値化して評価する審査です。この点数(結果)によって、受注できる工事の規模(ランク)が決まります。審査結果の有効期間は1年7か月ですが、公共工事を受注し続けるためには、実質的に毎年更新手続きを行う必要があります。申請には費用や手間がかかりますが、公共工事参入への必須条件です。
3. 入札参加資格審査申請
国土交通省や各都道府県、市町村などの名簿に登録するための申請です。多くの自治体では1〜2年ごとに定期的な更新時期を設けており、書類の提出が必要です。登録されると、Aランク、Bランクといった格付けがなされ、自社のランクに該当する工事の入札に参加可能となります。
公共工事入札の流れ

一般的な入札は、主に以下のような手順(フロー)で進みます。
1. 情報収集(案件を探す)
まずは入札案件を探すことから始めます。発注機関のホームページや、入札情報サービス(PPIなど)で検索・収集します。
2. 公告・設計図書等の取得
発注者が工事案件を公告します。参加希望者は、詳細が記載された仕様書、図面、設計書などのデータを取得します。
3. 積算・見積もり作成
公表された設計図書をもとに、材料費、労務費、機械経費などを正確に積み上げ、入札金額を決定します。疑問点があれば、早めに質問書を提出して解消しておく必要があります。
4. 入札・開札
指定された日時に札入れを行い、開札(結果発表)されます。
現在は国や多くの自治体でインターネットを使った「電子入札」が原則となっていますが、小規模な自治体や一部の案件では、依然として紙による入札が行われている場合もあります。
5. 落札者の決定・契約締結
最も条件の良い事業者が落札者となり、契約書を取り交わして工事請負契約(契約締結)を結びます。
入札・契約の種類と特徴

公共工事の契約方式は、大きく「競争入札」と「随意契約」に分類されます。
競争入札の主な方式
- 一般競争入札: 一定の条件(ランクや実績など)を満たせば、どの企業でも参加できる方式です。透明性が高く、国や都道府県の大規模工事では原則としてこの方式が採用されます。
- 指名競争入札: 発注者が実績や能力をもとに特定の数社を指名し、その企業間だけで競争させる方式です。過度な競争を防げるなどのメリットがありますが、透明性の観点から採用数は減少しつつあります。
入札によらない契約方式
- 随意契約: 競争を行わず、発注者が選定した特定の1社と契約を結ぶ方式です。災害時の緊急復旧工事や、その企業しか持っていない特殊技術が必要な場合、あるいは少額な工事などに限定して実施されます。
※具体的な運用ルールは、発注機関や自治体によって異なります。
近年の動向と入札戦略(2025年版)

近年の入札制度は、単なる価格競争から「品質確保」や「担い手確保」を重視する方向へ変化しています。
総合評価落札方式の主流化
「入札金額」だけでなく、「技術提案」や「企業の施工能力」を点数化し、価格と技術の総合評価で落札者を決める方式です。
国土交通省の直轄工事や、自治体が発注する一定規模以上の工事では、この方式が主流となっています。ここでは、価格の安さよりも「工期短縮の工夫」「安全対策」「地域貢献」などが評価の鍵を握ります。
最低制限価格制度とダンピング対策
過度な安値受注(ダンピング)を防ぐため、「最低制限価格」や「低入札価格調査制度」の適用が拡大しています。設定された基準価格を下回ると失格となる、または調査対象となるため、適正な積算能力がより一層求められています。
地域維持型契約の導入
除雪や道路維持など、地域の守り手としての役割を評価し、複数の業務を数年単位で包括的に発注する「地域維持型契約」なども増えています。これは主に国土交通省直轄工事で導入が進んでおり、都道府県や一部の市区町村にも広がりを見せています。
実務者が押さえておくべきポイント

現場監督として働く上で、入札の知識は実務にどう活きるのでしょうか。
- 設計図書の読み解き: 入札時に提示された条件(特記仕様書など)を正しく理解していないと、施工段階で契約外の作業が発生し、トラブルの原因になります。
- 工事評定点の重要性: 総合評価落札方式では、過去の工事成績(評定点)が得点源となります。自分の現場で良い評価点を得ることが、会社が次の入札で勝つための最大の貢献になります。
- 発注者意図の理解: なぜその工法や条件が入札で指定されたのかを知ることで、発注者との協議がスムーズになります。
まとめ:発注者支援業務という選択
公共工事の入札は、建設会社(受注者)にとって会社の存続をかけた重要なプロセスです。そこには、1円単位のコスト管理や、高度な技術提案など、シビアな競争が存在します。
一方で、この入札制度を「発注者側の視点」で支える仕事があることをご存じでしょうか。
「発注者支援業務」は、国土交通省や自治体のパートナーとして、予定価格の算出に必要な積算資料の作成や、工事監督の支援を行う仕事です。受注競争のプレッシャーとは異なり、公平で適正な公共事業の執行をサポートするという、公務員に準じた高い公益性を持っています。
現場経験を活かし、発注者を支えるプロへ
株式会社エムエーシーでは、国土交通省や地方自治体の発注者支援業務を数多く手掛けています。
現場を知り尽くした施工管理技士だからこそ、図面や現場状況を正しく読み取り、発注者をサポートすることができます。
競争の世界から、公共インフラを守る安定の世界へ。あなたの貴重な経験を、新しいステージで活かしてみませんか?
まずは採用サイトで、詳しい仕事内容や、当社で活躍する元・現場監督たちの声をご覧ください。
※掲載内容に関するご質問やエントリーは、Webフォームやメールから簡単に行えます。