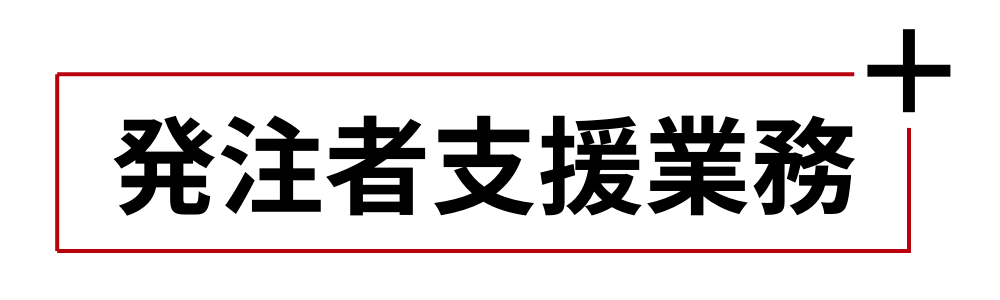「今の現場規模なら、自分は主任技術者でいいのか、それとも監理技術者が必要なのか?」
「資格者証などの書類確認や配置基準がいまいち複雑でわからない」
「将来のために、どちらの経験を積むべきか相談したい」
建設工事の現場において、必ずしも全員が配置されるわけではありませんが、法的に必ず置かなければならない技術者がいます。それが「主任技術者」と「監理技術者」です。この区分けは、建設業法(以下、法)や政令、施行規則などの法令に基づく厳格なルールがあり、少し複雑です。
しかし、この違いを正しく理解することは、現場のコンプライアンス(違反防止)を守るだけでなく、あなた自身の技術者としての市場価値を高めることにもつながります。
本コラムでは、2025年時点の最新情報をもとに、両者の違いや義務、特例などをわかりやすく説明します。目次を参照しながら、その資格や経験が「発注者支援業務」という安定したキャリアにどう活きるのかについても概要を確認していきましょう。
公共工事における主任技術者の役割

まず基本となる「主任技術者」について理解しましょう。
建設業法第26条第1項の規定により、元請・下請け、工事金額の大小に関係なく、建設業者が請け負ったすべての建設工事現場に設置(配置)しなければならないのが「主任技術者」です(※監理技術者を置く場合を除く)。
その役割は、当該工事現場における技術上の管理をつかさどることです。具体的には、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理などを行い、工事が適正に行われるよう従事する職人や下請負人を指導監督します。
つまり、主任技術者は現場の「技術的な責任者」であり、住宅から公共施設、大規模な工作物に至るまで、ものづくりの現場を支える最も基礎的かつ重要なポジションと言えます。
主任技術者に求められる資格と経験

主任技術者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
1. 国家資格等を有する者
1級または2級土木施工管理技士、建築士、技術士などの国家資格を有する者。
これらは知識と技術を公的に証明するものであり、資格者証の交付を受けていることが必須です。
2. 実務経験を有する者
大学、高等専門学校、高校などで、土木や建築などの指定学科(種目に係る学科)を卒業後、一定期間(大卒3年、高卒5年など)の実務経験がある者。
または、学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験がある者も該当します。
実務では、発注者への証明書類(実務履歴の資料など)の提出の手間を省くため、「2級施工管理技士」以上の資格保有者を配置するのが一般的であり、推奨されます。
主任技術者と監理技術者の違い

では、よく混同される「監理技術者」とは何が違うのでしょうか。最大の違いは「下請契約の総額」です。下記の表やポイントを参考に整理しましょう。
判定の基準(下請契約の請負代金総額)
元請業者が、その工事の一部を下請負人に発注する場合、その下請契約の合計金額が「5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上」になる場合は、主任技術者に代わって「監理技術者」を配置しなければなりません。
- 主任技術者: 下請合計金額が5,000万円未満、または下請けを使わない場合(原則すべての現場)
- 監理技術者: 下請合計金額が5,000万円以上となる工事
なお、この「5,000万円(建築8,000万円)以上」という金額要件は、「特定建設業の許可」が必要となる要件とリンクしています。つまり、公共性の高い大規模な工事で、鉄筋工事や型枠工事、とび、設備工事など多数の専門工事業者を束ねる特定建設業者が配置する技術者、それが監理技術者です。
また、監理技術者になるには、原則として「1級施工管理技士」などの上位資格に加え、登録講習実施機関が行う「監理技術者講習」の受講・修了(講習修了証の交付)が必要となるケースが多いです(※専任が求められる場合等)。
公共工事における主任技術者の業務内容

主任技術者が現場で常時行う主な職務(業務内容)は「4大管理」と呼ばれます。
- 工程管理: 工期通りに終わるようスケジュール(工程表)を調整・変更する
- 品質管理: 寸法や強度が設計図書の規格を満たしているかチェック・記録する
- 安全管理: 事故が起きないよう現場環境を整備し、KY活動などを実施する
- 原価管理: 予算内で工事が完了するようコストを管理する(※経営的な視点)
ここで重要な視点があります。主任技術者が作成したこれらの書類(施工計画書や品質管理記録など)を、「発注者側の立場」でチェック・審査しているのが、発注者支援業務の担当者です。
つまり、主任技術者としての実務経験があれば、発注者支援業務に転職しても即戦力として活躍可能なのです。
主任技術者の配置に関する法律と緩和措置

現場監督として働く上で避けて通れないのが「専任」のルールです。
専任が必要な現場(2025年改正)
個人的な請負契約の代金額が「4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上」の公共工事(および密接な関係のある民間工事)では、主任技術者や監理技術者を現場に専任で配置(常駐)させなければなりません(他の現場との兼任禁止)。
※建設業法施行令の改正により、専任を要する金額基準が引き上げられました。
制度改正と緩和等の例外
近年の法改正により、人材不足対策として要件が緩和されています。
例えば、ICTの活用や、補佐する者を置く「監理技術者補佐」の制度、あるいは近接する複数の現場(同一または近接した場所)を兼任できる「特例監理技術者」などの運用が認められる事例が増えています。
これらの詳細なルールは、政令やガイドライン(マニュアル)で定められています。違反すると営業停止などの処分や罰則の対象となるため、会社の事務担当や行政書士等と連携し、正確に把握しておく必要があります。
主任技術者になるためのステップ

現場代理人や作業員から、主任技術者へステップアップする一般的な流れ(手順)は以下のとおりです。
- 実務経験を積む: まずは現場の流れを理解し、写真管理や測量などの補佐業務に従事する。
- 2級施工管理技士を取得: これにより、一般建設業の営業所の専任技術者や、現場の主任技術者として認められます。
- 1級施工管理技士を取得: 監理技術者への道が開かれ、より大規模な現場を任されるようになります。
まとめ
主任技術者は、公共工事の品質と安全を守るためのキーパーソンです。その配置には「下請代金の額」や「請負契約の種類」による明確なルールがあり、適切な資格と経験が求められます。
もしあなたが、主任技術者や監理技術者としての資格・経験をお持ちなら、建設産業において非常に高い価値を持っています。
しかし、今の働き方に対して、
「責任が重すぎて精神的に休まらない」
「工事が終わるたびに転勤があり、家族と過ごせない」
といった悩みをお持ちではないでしょうか?
その貴重な資格と経験を、「発注者支援業務」で活かすという選択肢があります。
発注者支援業務は、国や自治体のパートナーとして、発注者側の立場で工事の品質管理や積算業務をサポートする仕事です。受注者(ゼネコン)のような利益追求のプレッシャーや転勤のリスクが少なく、公務員に準じた安定した体制で働くことができます。
あなたの資格を、より安定したステージへ
株式会社エムエーシーでは、国土交通省や地方自治体の発注者支援業務を専門に手掛けています。
主任技術者として培った「図面を読む力」「現場を管理する力」は、発注者を支える上で何よりの武器になります。
「現場監督の経験を活かして、ホワイトな働き方にシフトしたい」
そんな方は、ぜひ一度当社の採用情報をご覧ください。
検索エンジンで「株式会社エムエーシー」と調べるか、下記リンクから直接サイトへアクセスしてください。
※求人一覧や、転職した先輩社員のインタビュー記事も掲載中です。ご質問やエントリーは、WEBフォームやメールから簡単に行えます。