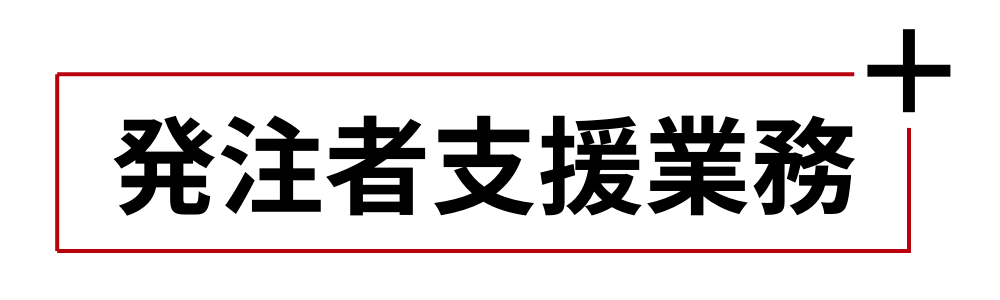「技術士の資格は役に立たないと聞きました。本当ですか?」
時折、このような質問を見聞きします。
そこでこの記事では、技術士の資格がなぜ役に立たないと言われるのか、取得するメリットなどを解説します。
技術士という資格に疑問を抱いている人は、ぜひ最後までご覧ください。
- 技術士の資格が役に立たないと言われる理由
- 技術士を取得するメリット
- 技術士が向いている人の特徴
MACは、建設業界の求人を多数取り扱っています。
資格の有無にかかわらず、優良求人を紹介しているので興味のある方は以下のLINEからお気軽にお問い合わせください。
技術士が役に立たないと言われる5つの理由

技術士が役に立たないと言われる理由は、大きく5つあります。
- 資格の知名度が高くない
- もし資格を取れなくても仕事はできる
- 責任が重くなる
- 必ず仕事に活かせるとは限らない
- 資格を取るまでに何年もかかる
技術士は本当に役に立たないのでしょうか?それぞれの詳細を確認します。
資格の知名度が高くない
技術士が役に立たないと言われるのは、資格の知名度が高くないからです。
技術士は五大国家資格の一つだと言われていますが、弁護士や税理士、建築士などと比較してそれほど多くの人に知られているとはいえません。
ただし、これは一般的にはあまり知られていないというだけで、建設業界ではすごい資格だと認知されています。
そのため、「一般的な知名度が高くない=役に立たない」と短絡的に判断するのは早計です。
もし資格を取れなくても仕事はできる
もし資格を取れなくても仕事ができることから、技術士は役に立たないと判断する人がいるようです。
医師、弁護士、税理士などは、資格を持っていなければ仕事ができないため、希少価値が高い印象を受けます。
その点、技術士は資格がなくてもスキルがあれば業務を行えるので、価値が低いと判断する人が一定数います。
責任が重くなる
技術士は、取得後以下のような義務や責務を負わなければなりません。
- 技術士の信用を傷つけたり、不名誉になったりする行為をしない
- 業務の秘密を漏らす、盗用してはいけない
- 公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することは避ける など
課せられる義務や責務は、これだけではありません。
大変な思いをしたのに、取得後さらに複数の義務や責務を課されることに抵抗がある人から評価が低いようです。
必ず仕事に活かせるとは限らない
技術士の試験範囲は膨大であり、合格するためには広範囲の知識を習得する必要があります。
しかし、それらの知識すべてが必ずしも仕事に活かせるとは限りません。
そのため、「技術士の資格は必要ないのでは?」と疑問を抱く人もいるようです。
技術士の資格が実務と乖離していると感じれば、役に立たないという認識につながるでしょう。
資格を取るまでに何年もかかる
資格を取るまでに何年もかかるため、技術士は役に立たないと言われることがあります。
たとえば、二次試験の出願で7年を超える実務経験を選択すれば、受けるまでに最低でも7年かかります。
さらに、二次試験の出願から合格発表まで1年かかったり、登録手続きが1年程度かかったりするなど、合計で10年以上かかるケースも珍しくありません。
10年あればほかの資格も取れるでしょう。
そのため、技術士は役に立たないと判断する人もいるようです。
技術士が役に立たないは嘘!取得するメリットは8つ

技術士が役に立たないと言われる理由をお伝えしました。
しかし、技術士が役に立たないと決めつけるのは早計でしょう。なぜなら、取得するメリットが8つもあるからです。
- 周囲からの評価が高くなる
- 専門性の高い仕事を任される
- 年収アップを期待できる
- 自己研鑽につながる
- 人脈作りにもつながる
- 転職で有利にはたらくことがある
- ほかの試験の受験にも役立つ
- 公共事業の入札で有利になることがある
これほどのメリットがある技術士を役に立たないという噂だけで諦めてしまうのは、もったいないかもしれません。
以下の記事で技術士のメリットについて詳しく言及しているので、併せてご確認ください。

技術士の取得が向いている人の特徴

技術士の取得が向いている人の特徴は、以下のとおりです。
- コンサルタントを目指している人
- 国や地方自治体から仕事を請け負う会社に勤務している人
- 技術者として大きな信頼を勝ち取りたい人
該当する方は、技術士の取得も検討してみましょう。
コンサルタントを目指している人
コンサルタントを目指している人は、技術士の取得が向いています。
建設業界において技術士は、トップクラスの資格です。
自分の知識やスキルを証明するのにぴったりの資格であり、実際コンサルタントを目指す人は技術士を取得する人が多い傾向にあります。
プロフェッショナルだと示したいなら、技術士は非常におすすめの資格です。
国や地方自治体から仕事を請け負う会社に勤務している人
国や地方自治体から仕事を請け負う会社に勤務している人も、取得を目指すとよいでしょう。
国や地方自治体は、工事を発注するときに入札を行っています。
その入札に参加するための条件として、技術士の配置が求められることも少なくありません。
そのため、国や地方自治体から仕事を請け負う会社では、技術士の存在はかなり重宝されます。
取得しておいて損はないでしょう。
技術者として大きな信頼を勝ち取りたい人
技術者として大きな信頼を勝ち取りたい人も、技術士の取得をおすすめします。
技術士は、周囲も認める最高峰の資格です。
取得するためには、単に知識があればいいだけではなく長い実務経験も要求されます。
そのため、周囲からは豊富な知識、スキル、経験がある人物だと評価され、大きな信頼を勝ち取れるでしょう。
技術士に関するよくある質問
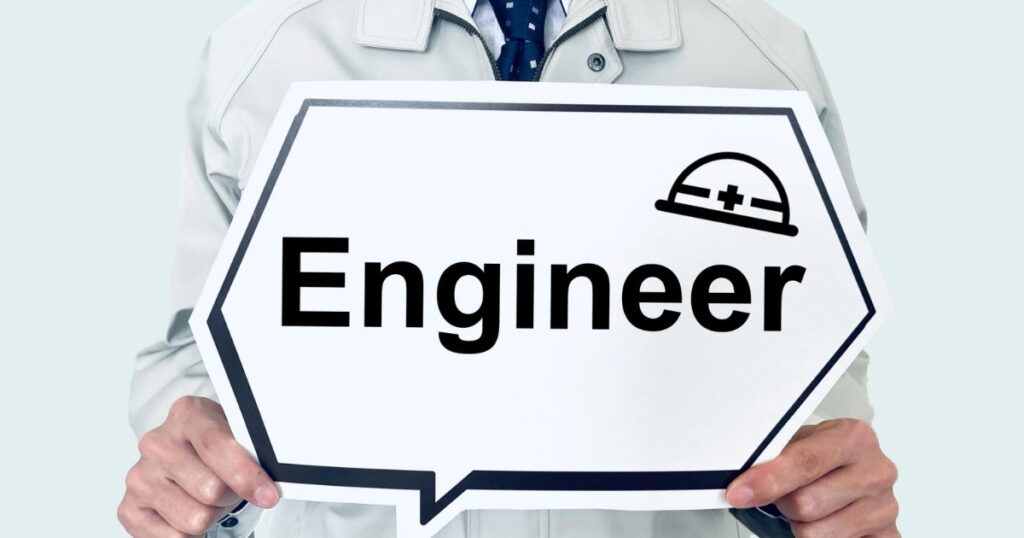
技術士に関するよくある質問は、以下のとおりです。
- 技術士は食いっぱぐれない資格ですか?
- 技術士になると何がすごいのですか?
- 技術士の難易度はどれくらいですか?
- 技術士の年収はどれくらいですか?
技術士への理解を深めるためにも、回答に目を通しておきましょう。
技術士は食いっぱぐれない資格ですか?
技術士は、食いっぱぐれない資格といえるでしょう。理由は、以下のとおりです。
- 取得難易度が高く、周囲から高く評価されるから
- 公共事業の入札で有利になることがあるから
誰でも簡単に合格できる資格ではなく、会社からも高い評価を得られるため、取得すれば食いっぱぐれる可能性は低いでしょう。

技術士になると何がすごいのですか?
資格一つで環境を大きく変えられる点は、技術士のすごさといえるでしょう。
たとえば、技術士になると、資格手当がもらえたり、任せられる仕事が増えたりして、年収が上がる可能性があります。
さらに、取得により昇進、昇給できたり、周囲からの信頼も得られるため日々の仕事がしやすくなったりするケースもあります。
このように、技術士を取得するだけで環境が一変するかもしれません。
以下の記事も併せてチェックしてみましょう。

技術士の難易度はどれくらいですか?
技術士試験は、一次試験が30%程度、二次試験が10%程度の合格率となっています。
RCCMの合格率が40%だと考えると、とくに二次試験はかなりハードルが高いといえるでしょう。
また、難易度を偏差値で表すと、一次試験が55〜56、二次試験が60〜64程度といわれています。
難易度が気になる方は、以下の記事もおすすめです。

技術士の年収はどれくらいですか?
厚生労働省が行った令和6年賃金構造基本統計調査によると、技術士の平均年収は615万円程度です。
一般的な平均年収が460万円ほどであることを考えると、かなり高い水準にあることがわかるのではないでしょうか。
平均年収からも技術士の希少価値の高さがわかります。
技術士の資格を取得するのも選択肢の一つ
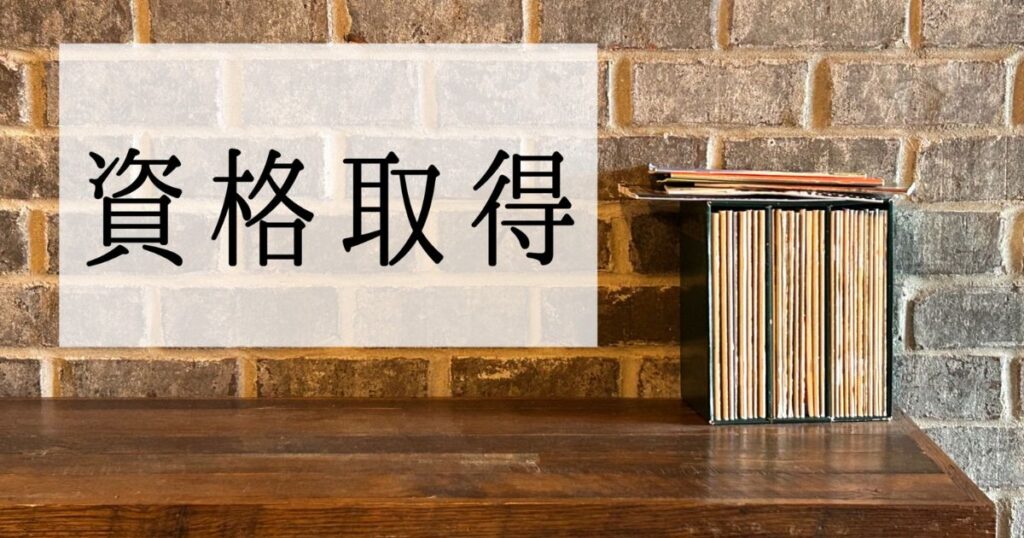
資格の知名度が高くない、責任が重くなるといった理由から、技術士は役に立たないと言われることがあります。
しかし、それは一方的な意見にすぎません。
技術士にはさまざまなメリットがあり、とても役に立つ資格です。
そのため、技術士の取得も選択肢の一つとして考えておくとよいでしょう。
ただし、資格がなくても仕事はできますし、条件の良い求人はたくさんあります。
とくに転職を考えている人はまずは技術士の資格を取るではなく、優良求人も同時に探しましょう。
私たちMACは、建設業界の優良求人を多数取り扱っています。資格の有無を問わないものもあるので、気になる人は以下のLINEからお気軽にお問い合わせください。