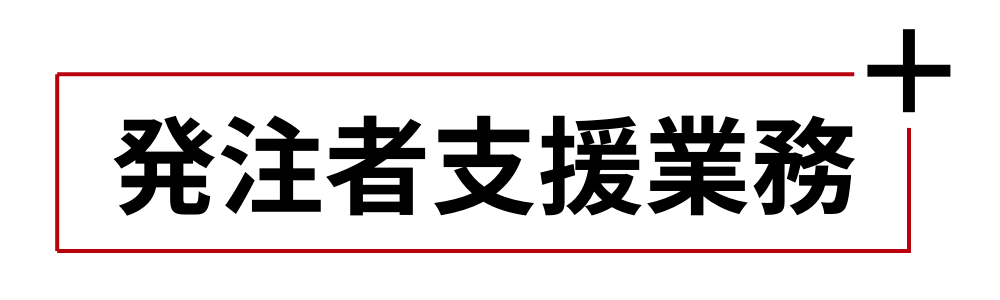「技術士補の試験って難しいのかな…?」
「そもそも技術士補って何の資格なの?」
技術職を目指す方の中には、このような疑問を抱いている人も多いのではないでしょうか。
技術士補とは、将来的に国家資格である「技術士」を目指すための第一歩として取得する資格です。
今回の記事では、以下の内容について解説します。
- 技術士補の試験はそもそも存在しない
- そもそも技術士補とは?
- 技術士補を取得するメリットとは?
技術士補について気になっている方は、ぜひ最後までご覧ください。
建設業界は、インフラ整備など多くの人に貢献できる仕事が多い傾向にあります。
転職を考えている方は、以下のリンクからMACへお気軽にご相談ください。
技術士補の試験はそもそも存在しない

「技術士補試験」という名称の試験は実在しません。
技術士補という資格は、試験単体で直接取得するのではなく、技術士第一次試験に合格するか、JABEE認定課程を修了した後、日本技術士会へ登録申請を行うことで初めて与えられます。
つまり、技術士補になるには試験の合格だけでなく、手続きも含めた一連の流れが必要であり、「試験に受かれば即資格が得られる」というわけではない点に注意が必要です。
そもそも技術士補とは?

技術士補は、技術士第一次試験の合格者やJABEE認定課程の修了者が、正式な登録手続きを経て名乗ることができる国家資格です。
業務では指導技術士の補佐として実務を経験し、将来の技術士を目指します。
技術士補としての登録により、第二次試験の受験に必要な実務年数が短縮されるなど、キャリア形成上のメリットもあります。
ただし、技術士資格を取得すると、技術士補としての登録効力は失われる点には注意しましょう。
技術士補と技術士の違い
技術士は、高度な専門性と実務能力を備えたプロフェッショナルに与えられる国家資格です。
一方の技術士補は、技術士になる前の「修習段階」に位置付けられ、主に実務経験を積む期間として活用されます。
イメージとしては、技術士補は見習い、技術士は一人前の専門家と捉えると分かりやすいでしょう。
それぞれの資格には、明確な役割と位置づけが存在することを理解しておく必要があります。
技術士補を取得するメリットとは?

技術士補を取得するメリットを見ていきましょう。
就職・転職で有利になる
技術士補の資格は、基礎的な知識と技術力を証明する手段として、多くの企業から評価されます。
特に建設業界などの技術職では、有資格者の存在が人手不足解消の一助となるため、採用や待遇面で優遇されるケースも珍しくありません。
応募できる職種の幅が広がるだけでなく、面接時のアピール材料にもなり、転職活動における競争力を高める要素となります。
技術士取得へのステップになる
技術士補のメリットとして、技術士第二次試験への近道となる点も挙げられるでしょう。
通常、第二次試験には7年以上の実務経験が求められますが、技術士補として登録し、指導技術士のもとで経験を積めば、最短4年で受験可能になります。
これにより、若いうちから技術士を目指すことが可能となり、キャリア形成を加速できるのは大きなメリットです。
キャリアアップにつながる
技術士補の資格は、専門性の証明として社内外での信頼性を高めやすくなります。
企業によっては、資格手当の支給対象となったり、昇進・昇格の条件に含まれたりすることも。
資格取得は自信にもつながり、より責任ある業務を任されるチャンスが広がるでしょう。
技術士補は、将来の技術士を見据えたキャリアパスの第一歩として非常に価値のある資格です。
技術士補になる方法

技術士補になるには、まず技術士第一次試験に合格するか、JABEE認定課程を修了する必要があります。
その上で日本技術士会に登録申請を行い、指導技術士による証明書を添付することで登録が完了します。
申請には登録免許税15,000円、手数料6,500円がかかります。
これらを経て登録簿に記載されると、正式に「技術士補」を名乗ることが可能です。
技術士試験の難易度

技術士試験の難易度をそれぞれ詳しく解説します。
技術士第一次試験
第一次試験は合格率30〜50%と比較的高めで、偏差値では55〜56程度とされています。
年齢や学歴に制限がなく、どなたでも受験できる点が特徴です。
試験科目は基礎・適性・専門に分かれており、全科目で50%以上の得点が必要です。
過去問の傾向をつかむことが合格のカギであり、最低でも5年分の演習を行いましょう。
技術士第二次試験
第二次試験は合格率が11%前後と低く、技術系資格の中でも最難関の部類に入ります。
偏差値では60〜64程度に相当するとされ、筆記と口頭の2段階試験です。
特に論文試験は配点比重が大きく、目安として600〜1,000時間の学習時間が必要とされます。
試験対策には、論述力と実務経験の言語化が欠かせません。
技術士の難易度について以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

技術士試験に合格するための勉強法

第一次試験はマークシート方式であるため、過去問の演習が非常におすすめです。
全科目で50%以上の得点が必要なので、苦手分野を作らずバランスよく学習することが合格への近道となるでしょう。
第二次試験では論文対策が極めて重要であり、日頃から業務経験を振り返りながら、キーワードを意識して論文練習を重ねることが求められます。
また、通信講座の活用も、効率的な勉強法のひとつです。
なお、MACでは「資格取得支援制度」を実施しております。
最大10万円の合格祝金をご用意しているので、詳細をぜひ以下のリンクでチェックしてみてください。
技術士補になった後にやるべきこと

技術士補となった後の最大の目的は、第二次試験の受験資格となる実務経験の取得です。
指導技術士のもとで最低4年の実務経験を積み、受験資格を得る準備を進めましょう。
また、この実務経験は口頭試験での自己アピールにも直結するため、日々の業務を記録に残すことが重要です。
並行して論文対策などの学習も行い、技術士資格の早期取得を目指しましょう。
まとめ:技術士補の難易度は高くはないが計画的な準備が必要!

技術士補自体の取得は、第一次試験の合格と登録申請によって可能であり、難易度はそれほど高くありません。
しかし、将来的に技術士を目指すなら、実務経験の積み方や学習計画を戦略的に組み立てる必要があります。
技術士補はあくまでスタート地点なので、計画的に行動し、キャリアの可能性を大きく広げましょう。
当社MACでは、建設業のご紹介・案内を行っております。
以下のLINEから無料で就職・転職相談が可能なので、お気軽にお問い合わせください。