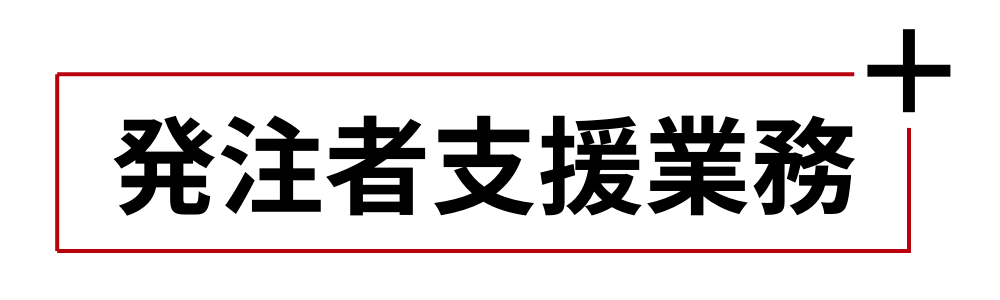技術士は難易度が高く、弁護士や医師などと並ぶ五大国家資格です。しかし、試験概要や資格取得のメリットなどがよくわかっていない人もいるのではないでしょうか?
そこでこの記事では、技術士についてわかりやすく解説します。
試験概要や資格取得のメリットのほかにも、平均年収や勉強法も紹介しますので、技術士に興味のある人はぜひ参考にしてみてください。
- 技術士とは何か・試験の概要
- 技術士のメリット
- 技術士の平均年収・勉強法
MACは、建設業界への転職をサポートしています。
「キャリアアップしたい」「条件の良い求人を探している」という人は、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。
技術士とは?制度の趣旨や部門を紹介

技術士は冒頭にもお伝えしたとおり、弁護士や医師などと並ぶ五大国家資格で、国内でも有数の資格です。
科学技術に関する高度な知識や応用能力を備えている者に技術士の資格を与えることで、社会の認識と関心を高めるほか、科学技術の発展を図るのが目的です。
技術士の試験は以下の部門にわかれています。
- 機械部門
- 航空・宇宙部門
- 化学部門
- 金属部門
- 建設部門
- 衛生工学部門
- 森林部門
- 経営工学部門
- 応用理学部門
- 環境部門
- 船舶・海洋部門
- 電気電子部門
- 繊維部門
- 資源工学部門
- 上下水道部門
- 農業部門
- 水産部門
- 情報工学部門
- 生物工学部門
- 原子力・放射線部門
- 総合技術監理部門(二次試験のみ実施)
建設業界に従事する人は、建設部門を受験することが多いでしょう。

技術士の試験|受験資格や難易度

ここからは、技術士の試験について紹介します。
第一次試験と第二次試験にわけて、それぞれの受験資格や合格率などを見ていきましょう。
技術士第一次試験について
技術士第一次試験の受験資格に、特別な定めはありません。
そのため、年齢や学齢、国籍などにとらわれることなく、誰でも受験できます。
建設部門の直近の合格率は35.8%でした。
| 年度 | 合格率(建設部門) |
|---|---|
| 令和2年度 | 39.7% |
| 令和3年度 | 28.9% |
| 令和4年度 | 41.2% |
| 令和5年度 | 36.7% |
| 令和6年度 | 35.8% |
過去5年の合格率は30〜40%程度で、難易度はやや高めといえるでしょう。
また、以下のような人は第一次試験の全部もしくは一部が免除されます。
- JABEE認定プログラム修了者
- 旧技術士試験制度下での合格者(一部免除)
- 中小企業診断士の有資格者(経営工学部門のみ一部免除)
- 情報処理技術者試験合格者(情報工学部門のみ一部免除)
免除制度を活用できるかどうか、事前に確認しておくことをおすすめします。

技術士第二次試験について
技術士第二次試験を受けるためには、第一次試験に合格しなければなりません。
加えて、下記いずれかの実務経験を満たす必要があります。
- 技術士補として、技術士の指導下で4年を超える実務経験
- 職務上の監督者の指導下で4年を超える実務経験
- 指導者・監督者の有無や要件を問わず、7年を超える実務経験
仮に、第一次試験に合格しても実務経験がなければ第二次試験は受験できません。
建設部門の直近の合格率は9.3%です。
| 年度 | 合格率(建設部門) |
|---|---|
| 令和2年度 | 11.7% |
| 令和3年度 | 10.8% |
| 令和4年度 | 11.0% |
| 令和5年度 | 10.4% |
| 令和6年度 | 9.3% |
過去5年の合格率は10%程度なので、第二次試験は非常に難易度が高いといえるでしょう。

技術士のメリットは8つもある

技術士には、大きく8つのメリットがあります。
- 周囲からの信頼を得られる
- 専門性の高い仕事ができる
- 年収アップを期待できる
- 自己研鑽につながる
- 人脈作りにも役立つ
- 転職で有利になることがある
- ほかの試験も受験しやすくなる
- 公共事業の入札で有利になることがある
技術士は難易度が高く、取得できれば周囲からの評価は大きく向上する可能性があります。結果、年収アップを期待できたり、転職で有利になったりするケースもあるでしょう。
さらに、人脈作りにも役立つうえ、ほかの試験も受験しやすくなるなど、さまざまな魅力があります。
以下の記事では、技術士のメリットをより詳しく解説しています。併せてご覧ください。

本当?技術士は役に立たないと言われる理由とは?

「技術士は役に立たない」という言葉を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?
実は、以下のような理由から技術士は役に立たないと言われることがあります。
- 資格自体の知名度が高くない
- 資格がなくても仕事はできる
- 取得後、責任が重くなることがある
- 必ず仕事に活かせるとは限らない
- 資格を取得するのに時間がかかる
たしかに、技術士の資格は取得したからといって、必ずしも仕事に活かせるとは限りません。さらに、資格がなくても仕事は可能です。
しかし、先ほどもお伝えしたとおり、技術士には数多くのメリットがあります。何も調べることなく、役に立たないという言葉を鵜呑みにするのはやめたほうがよいでしょう。

技術士の平均年収は600万円程度

厚生労働省が公開した「令和6年度賃金構造統計調査」を確認すると、技術士の平均年収が615万円程度だとわかります。
技術士の合格者のうち3〜4割は建設部門であるため、建設部門の技術士の平均年収も615万円に近い数字となるでしょう。
また、技術士の男女別の平均年収は以下のとおりです。
- 男性:637万円程度
- 女性:494万円程度
日本人の平均年収が460万円程度であることを考えると、技術士の年収は高い傾向にあるといえます。

技術士の資格を取得するための勉強法

技術士の資格を取得するための勉強方法を紹介します。
第一次試験と第二次試験にわけて紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
技術士第一次試験の場合
技術士第一次試験の合格を目指すなら、優先順位をつけて対策を行いましょう。
第一次試験は全科目50%以上得点しなければならず、得意科目だけでほかをカバーするといった戦略は取れません。
そのため、苦手科目を優先して勉強を進めるとよいでしょう。得意科目ばかり勉強して苦手科目を克服できなかったといったことにならないように注意が必要です。
また、第一次試験の勉強法として、過去問に繰り返し取り組むのもおすすめです。過去問へ取り組むことで出題傾向が把握でき、効率よく学習を進められます。
技術士第二次試験の場合
技術士第二次試験の場合は、論文対策をしっかりと行うのがおすすめです。論文の作成には訓練が必要で、正しい書き方について理解した上で何度も練習しましょう。
さらに、口頭試験の準備も怠ってはいけません。口頭試験の対策としては、スピーチ原稿の作成やビデオで撮影して振り返るのがおすすめです。
とはいえ、口頭試験は合格率も高いため、筆記試験を中心に学習を進めるとよいでしょう。
なお、MACでは「資格取得支援制度」を実施しております。
最大10万円の合格祝金をご用意しているので、詳細をぜひ以下のリンクでチェックしてみてください。
技術士に関するFAQ

技術士に関するFAQは、以下のとおりです。
- 技術士補の難易度は高いですか?
- 技術士補は将来なくなりますか?
技術士への理解をより深めたい人は、それぞれの回答にしっかり目を通しましょう。
- 技術士補の難易度は高いですか?
-
技術士補になるには、第一次試験に合格する必要があります。
そのため、技術士補の難易度は第一次試験の難易度同様、やや高めといえるでしょう。
ちなみに、技術士補試験という名称の試験はないため、注意が必要です。
あわせて読みたい 技術士補の難易度は高い?そもそも技術士補とは何なのか解説 「技術士補の試験って難しいのかな…?」「そもそも技術士補って何の資格なの?」 技術職を目指す方の中には、このような疑問を抱いている人も多いのではないでしょうか…
技術士補の難易度は高い?そもそも技術士補とは何なのか解説 「技術士補の試験って難しいのかな…?」「そもそも技術士補って何の資格なの?」 技術職を目指す方の中には、このような疑問を抱いている人も多いのではないでしょうか… - 技術士補は将来なくなりますか?
-
技術士補の制度は、さまざまな観点での見直しが進められています。
今後は、修習技術士への変更や登録期間の制限といった改革が進む可能性があります。
そのため、技術士補に関心のある人は制度の最新動向に注意を払っておく必要があるでしょう。
あわせて読みたい 技術士補は将来なくなる?今後の可能性や動向について解説 「技術士補って将来なくなるんじゃないの…?」「せっかく取得しても意味がないのでは?」 こんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。技術士補は技術士を目…
技術士補は将来なくなる?今後の可能性や動向について解説 「技術士補って将来なくなるんじゃないの…?」「せっかく取得しても意味がないのでは?」 こんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。技術士補は技術士を目…
技術士の資格を取得するかどうかは慎重に検討しよう

技術士の資格取得の難易度は高いといえます。とくに、第二次試験の合格率は10%を下回ることもあり、非常にハードルの高い資格です。
とはいえ、さまざまなメリットがあるのも事実です。そのため、目指すのは悪くないでしょう。
ただし、資格取得を優先すると、転職までに時間がかかってしまう可能性があります。転職が優先事項であるなら、勉強と並行で求人を探すのがおすすめです。
もし建設業界の優良求人を探しているなら、以下のLINEよりMACへご連絡ください。