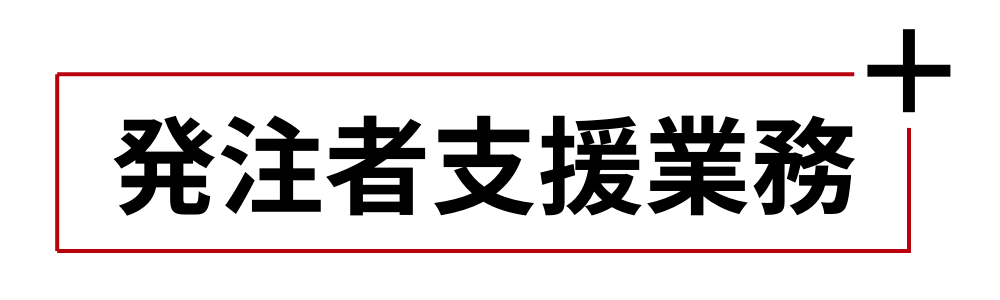「技術士ってすごいの?」
「いまいち技術士のすごさがわからない…」
技術士という言葉を聞いたことがある人の中には、上記のような疑問を持つ人もいるのではないでしょうか?
そこでこの記事では、技術士のすごさを理由とともに丁寧に解説します。
技術士という資格を取得するメリットについても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
- 技術士のすごさがわかる理由
- 技術士を取得するメリット
MACは、建設業界への転職に強い専門家です。
今後建設業界への転職を検討しているなら、以下のLINEからいつでもご連絡ください。
技術士が役に立たないと言われることがあるのはなぜ?

技術士は非常にすごい資格ですが、一部で役に立たないという噂を耳にします。
実は、技術士が役に立たないと言われる理由には、以下のようなものがあります。
- 知名度が高いとはいえない
- 業務独占資格ではない
技術士は弁護士や税理士などと比べると、知名度が高いとはいえません。
役に立たないわけではありませんが、知名度が高くないことからそのように評価されてしまうことがあります。
また、技術士は業務独占資格ではありません。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 名称独占資格 | 資格を持っている人だけが名乗れる資格 |
| 業務独占資格 | 資格を持っている人だけが独占的に仕事ができる資格 |
技術士は業務独占資格ではないため、資格がなければ仕事ができないというわけではありません。
そのため、「資格がなくてもできるなら必要ないのでは?」と思われることがあります。

建設部門の技術士のすごさがわかる5つの理由

とは言え、技術士はすごい資格であることに変わりありません。
建設部門の技術士のすごさがわかる理由は、大きく5つあります。
- 一次試験の合格率は30%程度
- 二次試験の合格率は10%を下回ることもある
- 二次試験は業務経験が必要
- 多くの勉強時間を捻出しなければならない
- 技術士は五大国家資格の一つに入る
それぞれの詳細を見ていきましょう。
一次試験の合格率は30%程度
建設部門の技術士の資格を取るためには、一次試験と二次試験に合格する必要があります。
そして、その一次試験の合格率は30%程度です。
| 年度 | 合格率(建設部門) |
|---|---|
| 令和2年度 | 39.7% |
| 令和3年度 | 28.9% |
| 令和4年度 | 41.2% |
| 令和5年度 | 36.7% |
| 令和6年度 | 35.8% |
実際、過去5年の一次試験の合格率を振り返っても、おおむね30%台であることがわかるでしょう。
また、その狭き門を通過した人は二次試験を受ける必要があり、さらに技術士のハードルを高めています。
二次試験の合格率は10%を下回ることもある
技術士の資格を取得するためには、一次試験に続いて二次試験にも合格する必要があります。
しかし、その合格率がなんと10%を下回ることもあるのです。
| 年度 | 合格率(建設部門) |
|---|---|
| 令和2年度 | 11.7% |
| 令和3年度 | 10.8% |
| 令和4年度 | 11.0% |
| 令和5年度 | 10.4% |
| 令和6年度 | 9.3% |
合格率はおおむね10%前後で推移しており、簡単に合格できる資格ではないことがわかります。
単に数字だけを見ても技術士のすごさがわかるのではないでしょうか?
二次試験は業務経験が必要
実は、技術士の二次試験には業務経験がなければなりません。
具体的には、受験申し込み時点で4〜10年の業務経験が必要です。
実際、二次試験の受験には以下のような規定があります。
| 総合技術監理部門以外の20部門を受験 | 総合技術監理部門を受験 | |
|---|---|---|
| 指導技術士や監督者の下で業務経験を積む場合 | 4年超 | 7年超 |
| 独自に業務経験を積む場合 | 7年超 | 10年超 |
業務経験が不要な資格と比べると、受ける時点でのハードルが高いといえるでしょう。
多くの勉強時間を捻出しなければならない
技術士の試験に合格するためには、かなりの勉強時間を捻出しなければなりません。
一次試験は300時間程度の勉強時間が必要だと言われており、1日2時間としても最低で5ヶ月はかかる計算です。
二次試験になるとさらに必要な時間は増加し、目安は1,000時間程度です。
いずれも目安なので、人によってはそれ以上の時間がかかるでしょう。
技術士は五大国家資格の一つに入る
実は、技術士は五大国家資格の一つです。
五大国家資格は、以下のとおりです。
- 技術士
- 弁護士
- 医師
- 公認会計士
- 弁理士
日本でもトップクラスに難易度の高い資格が並んでいるのがわかるでしょう。
技術士は、試験自体の難しさもそうですが、資格取得後の社会的な影響力の大きさから五大国家資格の一つに選ばれています。
弁護士や医師と同じレベルだと聞いたら、技術士のすごさがよりわかるのではないでしょうか?
技術士の難易度については、以下の記事を参考にしてみてください。

技術士を取得する5つのメリット

技術士を取得するメリットは、大きく5つあります。
- 社内ですごさが認められる
- 手当などで収入が増える可能性がある
- 人脈が広がる
- 監理技術者になれる
- 転職が有利に
技術士は持っていて損のない資格です。
メリットを一つずつ見ていきましょう。
社内ですごさが認められる
技術士の資格を取得すると、社内ですごさが認められます。
知名度が高くないとお伝えしましたが、建設業界で技術士といえば最高峰の資格です。
弁護士や医師と並ぶ五大国家資格を取得すれば、自然と社内での評価も上がるでしょう。
上司や同僚から一目置かれたり、取引先で話を聞いてもらいやすくなったりします。
手当などで収入が増える可能性がある
技術士になれた場合、手当などで収入が増える可能性があります。
たとえば、資格取得に対する手当の支給がある企業であれば、技術士の資格を取得すると毎月の給料があがります。
月に2万円の手当が支給される職場であれば、年間で24万円も年収が上がるため、非常に魅力的です。
人脈が広がる
技術士になると、人脈が広がるというメリットもあります。
実は、技術士は資格所有者同士が以下のようなグループを作って集まっています。
| グループ名 | 内容 |
|---|---|
| 日本技術士会 | 全国の技術士が集合する |
| 大学の技術士会 | 卒業生が集合して運営する |
| 企業の技術士会 | 企業内の技術士が集合して運営する |
専門外の技術士と意見交換することにより、モチベーションも高まるでしょう。
監理技術者になれる
建設部門の場合は、大規模な工事現場に配置しなければならない監理技術者になれます。
つまり、工事現場では重宝されるということです。
さらに、公共工事を入札する際に有利になる特典があるので、会社側から見れば手放したくない存在といえるでしょう。
技術士であることでほかのスタッフとの差別化を図れます。
転職が有利になる可能性がある
技術士の資格を取得すれば、転職が有利になる可能性があります。
技術士は、専門的な知識や技術を有していることを証明できる国家資格です。
たとえば、ほかの条件がすべて同じであれば、無資格者よりも技術士の資格を持つ人を選ぶ可能性が高いのは簡単に想像できるのではないでしょうか?
技術士の資格を持っていることが原因で、転職が不利になることはないでしょう。
技術士に関するよくある質問
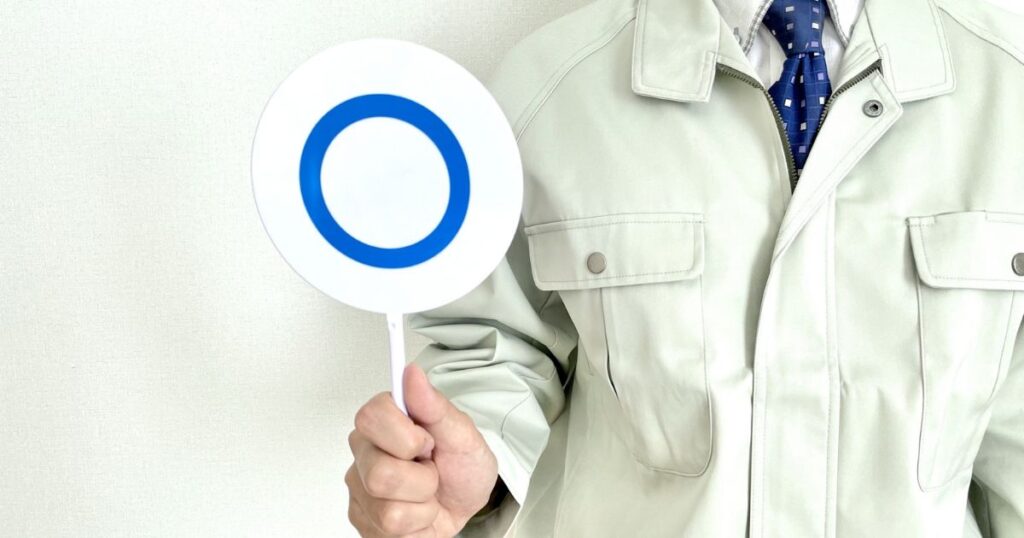
技術士に関するよくある質問は、以下のとおりです。
- 技術士の難易度は偏差値でいうとどれくらいですか?
- 技術士になるのは簡単ですか?
- 技術士は食いっぱぐれないですか?
技術士に関する理解をより深めたい場合は、よくある質問の回答にもしっかりと目を通しておきましょう。
技術士の難易度は偏差値でいうとどれくらいですか?
技術士の難易度は、偏差値でいうと一次試験が55〜56、二次試験が60〜64程度だといわれています。
大学でいうと、明治大学や青山学院大学などです。
ただし、偏差値はあくまで参考であり、その偏差値以上あるからといって必ず受かるとは限りません。
とくに、二次試験はしっかりと勉強時間を取る必要があります。
技術士になるのは簡単ですか?
技術士になるのは簡単ではありません。
二次試験に限れば、合格率は10%程度です。
勉強時間も合計で1,000時間以上が必要になるのが一般的です。
技術士になろうと決めたら、ある程度大変なのは覚悟したほうがいいかもしれません。
技術士は食いっぱぐれないですか?
技術士は、現時点では食いっぱぐれない資格といえるでしょう。
技術士を取得できるほどの知識やスキルがあれば、職場内でも重要なポジションである可能性が高く、仕事がなくなる確率は低いといえます。
ただし、取得するのが難しいので、計画的に行動する必要があります。
建設業界への転職ならMACにご相談ください

技術士は合格率が10%を下回ることもある難関資格で、弁護士や医師と並ぶ五大国家資格の一つです。
一般的に知名度が高い資格ではありませんが、取得すれば収入が増えたり、転職で有利になったりします。
技術士は役に立たないと言われることがありますが、メリットの多い資格です。
MACは、建設業界への転職をサポートしています。
技術士の資格を取得するかどうかにかかわらず、転職を検討している人はお気軽にご相談ください。