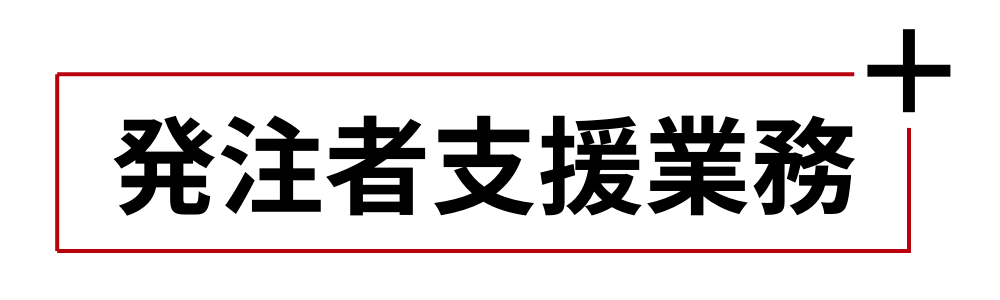「技術士補って将来なくなるんじゃないの…?」
「せっかく取得しても意味がないのでは?」
こんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。技術士補は技術士を目指すうえでの重要なステップですが、時代の変化や制度の見直しによって将来の立ち位置がどうなるのか、気になるところです。
そこでこの記事では、以下の内容について解説します。
- そもそも技術士補とは?
- 技術士補が「なくなる」と言われる理由
- 技術士補で検討されている課題
資格取得を検討している方やキャリアに不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
MACは、建設業界への転職をサポートしています。
さまざまな求人を取り扱っているので、技術士に限らず転職を考えている方はお気軽にお問い合わせください。
そもそも技術士補とは?

技術士補とは、将来的に技術士を目指す人材を育成するために設けられた国家資格です。
技術士法では、「技術士となるのに必要な技能を修習するため、技術士を補助する者」と定義されており、あくまで技術士の前段階の資格として位置づけられています。
資格を取得するには、技術士第一次試験に合格するか、文部科学大臣が指定した教育課程(JABEE認定課程など)を修了したうえで、日本技術士会に登録を申請する必要があります。
登録後は指導技術士の監督のもとで実務経験を積み、技術士に求められる専門的なスキルや倫理観を体系的に身につけていきます。
技術士補が「なくなる」と言われる理由

技術士補が「なくなる」と言われる理由について見ていきましょう。
技術士補で二次試験を受験するルートを選択する人が少ない
技術士補の制度が見直される主な理由の一つは、制度利用者が極めて少ない点にあります。
技術士第二次試験の受験資格には複数のルートがありますが、「技術士補として4年以上の実務経験を積む」方法を選択する人は、全体の2%未満に過ぎません。
多くの受験者は、7年以上の実務経験によって受験資格を得ており、制度の活用が進んでいないのが実情です。
この利用率の低さから、制度の存在意義が問われているといえます。
技術を教える指導者(指導技術士)が身近にいないことが多い
技術士補として登録するには、同一部門の「指導技術士」を見つけ、その指導のもとで実務経験を積む必要があります。
しかし、勤務先に該当する技術士がいないケースも多く、登録自体が難しい状況があります。
このように、制度を活用するうえでの環境整備が不十分であることが、技術士補制度の利用率低下を招いている大きな要因といえるでしょう。
技術士補で検討されている課題

技術士補という名称が、制度の本来目的である「技能の修習」を十分に伝えていないとの指摘があります。
そのため、第一次試験合格者に対して「修習技術士(仮称)」という名称に変更する案が検討されています。
これにより、制度が単なる補助業務の資格ではなく、技術士へのステップであることを明確にしようという狙いがあります。
日本技術士会のアンケートでは、この見直しを支持する意見が多数を占めているため、将来的には、修習技術者やJABEE修了者と統合した上で、別の名称になる可能性も指摘されています。
技術士補に関する今後の制度改正の可能性と動向

技術士補に関する今後の制度改正の可能性と動向について解説します。
修習技術士の名称変更
「修習技術士」への名称変更の可能性 技術士補制度を維持しつつ、名称を「修習技術士」へと変更する案が有力視されています。
これは、現行制度が「補助者」という誤解を招いているという課題に対応するもので、技術士を目指す段階であることを強調するための施策です。
制度の意義を再認識させ、利用の促進につなげることが期待されています。
技術士補の登録期間の制限の可能性
技術士補に登録したまま長年技術士にならない人が一定数存在することから、登録期間に上限を設ける案も浮上しています。
たとえば、登録後15年を超えると合格率が著しく低下するという実態から、15年程度で登録資格を失効させることで、早期の第二次試験受験を促す方策が検討されています。
この対策により、多くの技術士育成に成功する効果が期待できるでしょう。
指導技術士の見直し
技術士補登録に必要な「同一技術部門の指導技術士」の確保が難しいことが、制度利用の大きな障壁となっています。
対策として、指導技術士の要件緩和、あるいは部門を限定しない形への制度改正が検討されています。
他の受験ルートでは部門制限がないこととの整合性をとる目的も含まれており、今後の議論の焦点となるでしょう。
技術士補の価値は本当にないのか?

一部では「技術士補は肩書きだけで役に立たない」といった声もありますが、それは正確とはいえません。
技術士補は、将来の技術士となる人材を育成する国家資格であり、第一次試験に合格したことを示す客観的な証明でもあります。
指導技術士の監督下で業務を補助する制度により、技術士に求められる実務能力や倫理観を体系的に学べる点も見逃せません。
また、技術士第二次試験の受験に必要な実務年数が短縮されるなど、キャリア形成上の具体的なメリットもあることから、技術士補は決して価値のない資格とはいえないのです。
なお、MACでは「資格取得支援制度」を実施しております。
最大10万円の合格祝金をご用意しているので、詳細をぜひ以下のリンクでチェックしてみてください。
まとめ:技術士補に関する今後の制度改正の可能性と動向に関するニュースは常にチェック!

技術士補制度は、利用率の低さや制度上の課題により、様々な観点での見直しが進められています。
特に指導技術士の確保や名称の誤解といった問題が、制度の有効性を損なっている要因とされています。
今後は「修習技術士」への変更や、登録期間の制限といった改革が進む可能性もあり、制度の最新動向に注目しておくことが重要です。
なお、MACは、建設業界への転職をサポートしています。
さまざまな求人を取り扱っているので、技術士に限らず転職を考えている方はお気軽にお問い合わせください。