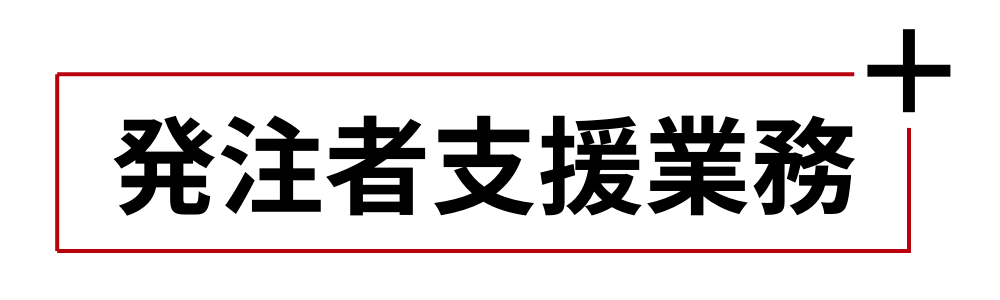「転職サイトで建築士を見かけたけど、どんな仕事をするの?」
「建築士って設計以外にどのような業務をするの?」
この記事では、上記のような疑問を解決します。
建築士の主な仕事内容や1日のタイムスケジュールなどを解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
- 建築士の主な仕事内容
- 建築士の仕事の流れ
- 建築士のやりがい
建設業界への転職をサポートしている私たちMACでは、さまざまな求人を扱っています。
建設業界に興味のある人は、以下のLINEからお気軽にお問い合わせください。
建築士は大きく3種類に分けられる

実は、建築士は大きく3種類に分けられます。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 木造建築士
建築士は持っている資格によって、設計できる建物の規模や構造が異なります。
それぞれの詳細を見ていきましょう。
一級建築士
一級建築士は、国土交通大臣から認可を受けており、設計する建物に制限がないのが特徴です。
たとえば、学校や病院など延べ面積が500平方メートル以上ある建造物、高さが16m以上の建物は一級建築士でなければ設計できません。
マンションや高層ビルの設計も同様です。
二級建築士
二級建築士は、都道府県知事から認可を受けており、設計できる建物に制限があるのが特徴です。
たとえば、以下の条件を満たす建物であれば設計できます。
- 高さ16m以下かつ2・3階の延べ面積1,000平方メートル以下の木造建築物
- 高さ16m以下かつ延べ面積300平方メートル以下の鉄筋コンクリート・鉄骨等の建物
- 500平方メートル以下の公共施設 など
二級建築士は、主に住宅の設計を想定している資格です。
木造建築士
木造建築士は、都道府県知事から認可を受けており、設計できるのは木造建築物のみです。
延べ面積が300平方メートル以下、かつ2階以下の木造建築物なら設計可能です。
一級建築士や二級建築士と比べると、業務範囲は比較的限定されます。
建築士の仕事内容をわかりやすく解説

建築士の主な仕事内容は、以下のとおりです。
- 設計
- 工事監理
- その他
どのような仕事をするのか詳しく見ていきましょう。
設計
建築士と聞けば、設計をイメージする人も多いでしょう。
設計業務では、構造や設備などを決定し、工事に必要な設計図および仕様書を作成します。
さらに、建築設計は以下のように分けられます。
- 意匠設計:建物のデザインを決定する
- 構造設計:骨組みを決定する
- 設備設計:水道や電気などのインフラ設計をする
また、設計は、建物の用途だけではなく、発注者の希望、予算などさまざまな要素を考慮して、作業を進めると覚えておきましょう。
工事監理
工事監理は、設計図あるいは仕様書に沿って適切に工事が行われているかを確認する業務です。
たとえば、工事現場に足を運び、担当者と打ち合わせしたり、接合箇所を確認したりします。
もし工事が設計図に沿って行われていなければ、建築士は工事監理者として是正を求めなければなりません。
また、工事監理が終わったら報告書を作り、施主に終了した旨を伝えます。
その他
設計や工事監理のほかに、事務作業があります。
事務作業には、以下のようなものがあります。
- 建築許可申請書の作成
- 道路使用許可申請の作成
- 契約書の監修
- 契約内容の折衝
- 建物の調査鑑定 など
主な仕事は設計と工事監理ですが、ほかにもさまざまな業務を担当する可能性があることを覚えておきましょう。
建築士の仕事の流れは?|1日のタイムスケジュールも紹介

ここでは、建築士の仕事の流れを紹介します。
- 打ち合わせ
- 建物の設計
- 工事監理
- 事務作業
それぞれの詳細を見ていきましょう。
さらに、1日のタイムスケジュールの例も紹介します。
打ち合わせ
施主から建築の依頼を受けたら、打ち合わせを実施します。
建物のデザインや部屋の広さ、予算など、要望を詳しく聞きます。
施主とのイメージのすり合わせが済んだら、次のステップに進むのが一般的です。
建物の設計
施主との打ち合わせで建物の完成形をイメージできたら、実際に設計に入ります。
設計ソフトであるCADを使って図面の作成を進めます。
建物の設計では内部の細かいデザインまで決めるので、施主との意見交換は積極的に行うことが重要です。
工事監理
設計図ができたら実際に工事に入っていきますが、建築士は工事監理者として施工に立ち会います。
工事が設計図どおりに進んでいるか確認し、もし図面どおりでない場合は是正するように指摘します。
専門的な知識を持たない施主の代わりに、安全性と品質をチェックするのが建築士の大事な役割です。
事務作業
工事が完了したあとは、事務作業を行います。
建築士は完成後の建物のチェック、料金の支払いなど、適切に処理を進めます。
建物の引き渡しが完了したら、建築士の仕事は終わりです。
就職先によってはやや流れが異なることもありますが、おおよその流れは「打ち合わせ→設計→工事監理→事務作業」と覚えておきましょう。
1日のタイムスケジュール
ここで、建築士の1日のタイムスケジュールを簡単に紹介しておきます。
たとえば、住宅設計の建築事務所で働く建築士の1日のスケジュールは以下のとおりです。
- 8:00:出社
- 9:00:朝礼・メール確認
- 9:30〜12:00:図面の作成
- 12:00〜13:00:昼休憩
- 13:00〜14:00:工事監督と打ち合わせ
- 14:30〜17:00:図面の作成
- 17:00〜:次の日の準備
- 17:30:帰宅
図面の作成がメインではありますが、打ち合わせなどもあるため、建築士の仕事はやや流動的です。
1日のスケジュールが大きく変わることもあると認識しておくとよいでしょう。
建築士にやりがいはあるの?

ここまでは建築士の仕事について触れてきましたが、実際やりがいはあるのでしょうか?
実は、建築士には以下のようなやりがいがあります。
- ゼロから何かを作る楽しさを経験できる
- さまざまな人に利用される喜びがある
- 女性も活躍できる
それぞれ見ていきましょう。
ゼロから何かを作る楽しさを経験できる
建築士は、ゼロから何かを作る楽しさを経験できます。
実際、建物の図面を作り、工事監理を行い、その建物が完成したときの達成感や充実感は想像以上です。
また、施主の希望を取り入れて設計しているので、完成したときの喜びを人と共有できるというメリットもあります。
ものづくりが好きな人は、とくに大きなやりがいを感じられるかもしれません。
さまざまな人に利用される喜びがある
建築士が設計した建物は、何年にも渡りさまざまな人に利用されます。
多くの人に利用されることで、建築士として大きな喜びを感じられます。
住宅に限らず、公共施設や商業施設など数多くの人が利用する建築物の設計に携われば、大きなやりがいを実感できるでしょう。
女性も活躍できる
建築士は女性も活躍できる職業です。
より良い設計をして、適切な工事監理が行えるのであれば、男女関係なく活躍できます。
「ものづくりが好き」「多くの人に喜ばれる仕事がしたい」という人は、男女関係なく建築士が向いているかもしれません。
建築士の収入はどれくらい?

建築士の収入は資格によっても異なりますが、平均年収はおおむね350〜700万円です。
一般的な日本人の平均年収は460万円程度です。
一級建築士の平均年収は703万円とのデータもあるので、建築士の年収は比較的高い傾向にあるといえるでしょう。
参考:政府統計の総合窓口 「賃金構造基本統計 調査令和元年以前 職種DB第1表」
ただし、資格や就職先によっては一般的な平均年収を下回ることもあります。
年収を少しでも上げたいなら、一級建築士の取得や大手企業に転職するなどの工夫が必要です。
年収を上げる方法については、以下の記事が参考になります。

建築士の主な転職先|建設業界では需要が大きい

ここからは、建築士の主な転職先を紹介します。
- ゼネコン
- 工務店・ハウスメーカー
- リフォーム会社
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
ゼネコン
ゼネコンは、大規模な土木および建築工事を請け負います。
そのため、建物の設計について制限のない一級建築士は重宝されるでしょう。
一方で、建物の設計に制限のある二級建築士も、スキルや実績によっては大手ゼネコンから必要とされる場面があります。
ただし、ゼネコンは得意としているジャンルが異なるので、事前に企業研究してから転職先を選ぶのがポイントです。
工務店・ハウスメーカー
工務店やハウスメーカーも建築士の主な転職先になります。
とくに、住宅や小規模な施設を扱うハウスメーカーや工務店は、二級建築士から人気な傾向があります。
ハウスメーカーや工務店に転職して実績を積みつつ、一級建築士を目指すといった方法もいいかもしれません。
リフォーム会社
リフォーム会社も主な転職先の一つです。
日本の住宅の多くは木造なので、リフォーム会社では木造建築士も活躍しています。
ただし、リフォーム会社ごとに得意としているジャンルは異なるので、転職を考えるなら事前調査は必須です。
建設業界の転職ならMACにご相談ください

建築士の主な仕事は、設計と工事監理です。
ただし、必要に応じて道路使用許可申請の作成や契約書の監修といった事務作業も発生することは覚えておきましょう。
建築士は、ゼロから何かを作る楽しさを経験できたり、女性も活躍できたりするうえ、年収も比較的高い傾向にあります。
そのため、建築士としての転職も有力な選択肢となるでしょう。
私たちMACは、建設業界の魅力的な求人を多く取り扱っています。
建築士の資格がなくても応募できる求人は多数あるので、気になる人は一度以下のLINEからご連絡ください。