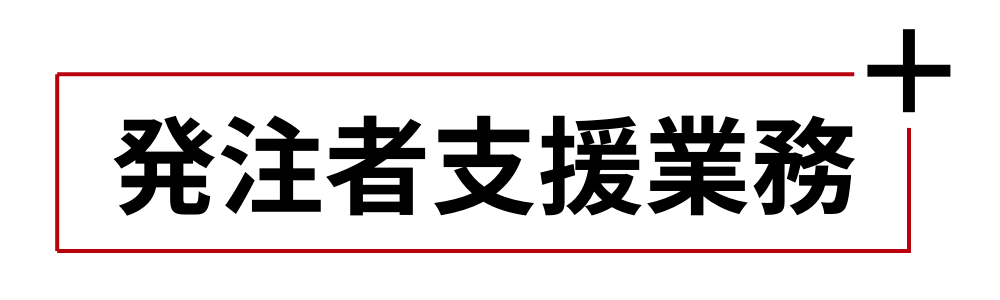「建設業に興味はあるけど、就職しても大丈夫かな?」
「就職活動を始める前に、建設業の仕事について理解したい!」
はじめての就職活動なので、建設業への就職に関して不安を感じるのも無理はありません。
後悔しない就職活動をするためには、建設業に関して理解を深めることが重要です。
今回の記事では、建設業に就職を決めた理由を7つ厳選して解説します。
今後の建設市場予想や主な就職先、建設業に就職するときのチェックポイントも紹介。
安心して就職活動をスタートさせるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
- 建設業に就職を決めた理由
- 建設業の主な就職先
- 建設業に就職するときのチェックポイント
当社MACでは、建設業のご紹介・案内を行っております。
以下のLINEから無料で就職・転職相談が可能なので、お気軽にお問い合わせください。
今後の建設市場予想

今後の建設市場予想について、解説します。
一般財団法人 建設経済研究所と一般財団法人 経済調査会 経済調査研究所が公表している「建設経済モデルによる建設投資の見通し(2025年1月)」には、建設経済の予測結果が掲載されています。
2025年度の建設投資は、75兆5,800億円と予測。
2024年度の建設投資が74兆1,600億円なので、前年度比1.9%増です。
「政府分野投資」と「民間建設投資」の増減については、以下のように予測されています。
【2025年度の政府分野投資と民間建設投資の予測】
| 種別 | 投資額 |
|---|---|
| 政府分野投資 | 24兆7,700億円(前年度比4.2%増) |
| 民間建設投資(住宅投資) | 17兆3,800億円(前年度比2.1%増) |
| 民間建設投資(非住宅投資) | 18兆3,200億円(前年度比3.2%増) |
建設投資額(名目値)の推移を見ると、2014年から右肩上がりで増加していることから、建設業は10年間成長し続けてきたといえます。
成長の見込みがある業界を選ぶのも、就職時にチェックしておきたいポイントです。
土木工学を学んでいた大学時代の筆者も、就職活動を始めるときに市場予測を調べていました。
建設業は今後も需要が高まると聞いたことがあるかもしれませんが、実際にデータがあると安心できますよね。
ただし、2025年度の建設投資は実績値ではないため、数値は今後変わる可能性もあります。
建設業への就職を考えている方は、建設業の未来を知るヒントとして、建設市場の動向をチェックしてみてくださいね。
建設業に就職を決めた理由7選

建設業に就職を決めた理由を7つ厳選してご紹介します。
就職を決める理由を明確にすることで、企業選びで大切にしたいことがわかったり、キャリアプランを描きやすくなったりするでしょう。
過去に建設業で働いていた筆者の経験を交えてお伝えするので、建設業への就職を考えている方は参考にしてみてください。
大学で学んだ知識を活かせる
建設業に就職すると、大学で学んだ知識をダイレクトに業務に活かせます。
大学では、構造力学・土質力学・水理学・コンクリート工学など、土木工学の基本的な知識を習得してきたのではないでしょうか?
また、測量実習やCADを使った図面の作成、コンクリートの配合設計など、実習を経験してきた方もいるかもしれません。
土木工学の基本的な知識は、建設業の仕事で使う場面も多々あります。
筆者は、大学で土木工学を専攻していました。
建設業に就職した新入社員時代を振り返ると、特にコンクリート工学やCADの操作方法は、大学時代に学んでいて良かったと感じています。
基礎知識が身についていたので、先輩の仕事を任せてもらうことも多かったです。
大学時代に身につけた知識や、スキルでは現場で対応できないことも事実。
ただ、学生時代に身につけた知識やスキルを活かして仕事ができるので、即戦力となれるのは間違いないでしょう。
大きな達成感を得られる
大きな達成感を得られるのも、建設業に就職する魅力の1つです。
建設工事を進めるためには「調査・計画」「設計」「施工」「維持管理」など、さまざまな工程があります。
たとえば「施工」を例に見てみましょう。
着工から竣工まで数ヶ月〜数年かかるなど、土木構造物は時間をかけてつくられます。
タイムラプスカメラで日々の施工状況を撮影したことがありますが、物語が進んでいるようで感動しました。
ヘルメットのあご紐で日焼けしながら奮闘した真夏の現場、防寒服を着ても寒さを感じた真冬の現場。
自然の厳しさを感じながら仕事をするからこそ、完成時の達成感は言葉では言い表せないものです。
筆者も、はじめて主任技術者として関わった建設工事では、完成時に涙を流したことを覚えています。
このように大きな達成感を得られるのも、建設業で仕事をする醍醐味です。
多くの人と関わって仕事ができる
建設業に就職すると、多くの人と関わって仕事ができます。
1人で進められる建設プロジェクトは存在しないといえるほど、多くの人とチームになって仕事を進めます。
建設業に就職すると、発注者・建設会社・建設コンサルタントと関わる機会が多くなるでしょう。
さらに、専門工事会社・測量会社・資材メーカーなど、自社以外の人と一緒に仕事をすることもあります。
チームで仕事をするのが好きな方にとって、建設業の仕事は魅力的に感じるでしょう。
さまざまな分野の人と仕事をする中で、自分自身も知識を得られたり、スキルを習得できたりすることもあります。
筆者は、関東の高校を卒業していますが、東北地方の建設現場でOBさんにばったり会いました。
お互いに所属する会社は違いますが、出来形管理や安全管理などをOBさんから丁寧に教えてもらいました。
「会社に関係なく多くの人と関わって仕事をするのっていいな」と感じながら、仕事を進められたのを覚えています。
1人で黙々と仕事をしたいのかチームで話し合いながら進めたいのか、建設業に就職する前に考えをまとめておくと良いでしょう。
経験を積むほど成長を感じられる
建設業に就職すると、経験を積むほど成長を感じられるのも特徴です。
建設業では、学生時代に学んだ土木工学の基礎知識を活かせますが、先輩や上司から話を聞いても専門用語の理解ができないことも多々あります。
また、気をつけるポイントがわからず失敗することもあるでしょう。
筆者も、入社1年目の頃に担当した図面作成でミスをしたのを覚えています。
VP管(硬質ポリ塩化ビニル管)の位置が発注図面と施工資料で合っていないにもかかわらず、発注図面が正しいと勝手に判断してしまいました。
発注図面と施工資料をどちらも確認するように先輩に注意され、手元にあるデータをすべて確認する重要さに気づきました。
建設業に就職し、働いていくことで日進月歩で進化する自分を実感できるでしょう。
国の大規模プロジェクトに参加できる
国の大規模プロジェクトに参加できるのも、建設業に就職する魅力の1つです。
国の大規模プロジェクトは各メディアで報道されることも多いため、自分の仕事に誇りを持てるでしょう。
自分が関わった建設プロジェクトが終わってからも、人々が注目する観光スポットになることもあります。
筆者も国の大規模プロジェクトに何度か参加したことがあります。
計画から施工まで関わってきた道路工事に関する建設プロジェクトで、新聞や雑誌に取り上げてもらいました。
「日本中が注目している建設プロジェクトに関われるなんて嬉しい」と感じました。
歴史に名を刻めるのも、建設業で仕事をする魅力といえるでしょう。
実際、夜間作業で進めた建設プロジェクトだったので、作業が思うように進まず作業環境の違いに気づいた経験でもあります。
夜間は視界が悪く、大型トレーラーなどの車両による交通事故のリスクも高まるため、昼間とは違う点で現場の安全対策を行うのが大変だったと記憶しています。
社会貢献度の高い仕事ができる
社会貢献度の高い仕事ができるのも、建設業に就職するきっかけになることも。
筆者たちが快適な生活を送れるのは、社会資本が整備されているからといっても過言ではありません。
自宅の水道の蛇口をひねると水が使えるのは、水道管を設置するなど上水道工事が行われているおかげです。
また、道路工事や鉄道工事のおかげで、日本全国へ気軽に旅行ができます。
建設業で仕事をする人々がいるからこそ、筆者たちは不自由なく生活ができています。
このように、建設業の仕事は社会貢献度が高いため、仕事のやりがいにもつながるでしょう。
建設工事といえば「ご迷惑をおかけしています」の看板をイメージする方もいるでしょう。
片側交互通行や車両通行止めなどをお願いするとき、困った顔をしている人に出会ったことがありますが、地元住民から「ありがとう」と感謝の言葉をもらったことがあります。
建設業に就職すると、人々から「ありがとう」という言葉をかけてもらいながら仕事ができます。
自然災害に強いインフラ整備に関われる
建設業では、自然災害に強いインフラ整備に関われます。
自然災害が多い日本では、人々が安心して暮らせるまちづくりを進める必要があります。
たとえば、マグニチュード9.0の巨大地震の甚大な被害をもたらした「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」では、多くの尊い命が失われました。
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震をはじめとする自然災害を防ぐことができませんが、人々が安心して暮らせるように災害リスクを減らすことはできます。
災害リスクを減らすために建設業ができることは、防波堤の整備や河川整備などの自然災害に強いインフラ整備です。
被害を受けた地域では、地方自治体を中心に復旧・復興工事が進められてきました。
医療従事者は人々の命を救う仕事。
一方で建設業従事者は、自然災害から人々の命を守る仕事といえるでしょう。
【建設業に就職】主な就職先

建設業の主な就職先をご紹介します。
建設業への就職といっても、さまざまな就職先があります。
筆者も、就職活動をするまでわからなかった就職先がありました。
就職活動を始める今のうちに、建設業の就職先には選択肢がたくさんあることを知っておきましょう。
企業選びの幅を広げるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
官公庁・公社・機構
「官公庁・公社・機構」は、建設業の就職先の1つです。
それぞれの違いは、以下のとおりです。
【官公庁・公社・機構】
| 組織・団体名 | 具体的な組織・団体 |
|---|---|
| 官公庁 | 国や地方自治体などの役所 (例)国土交通省・都道府県庁や市町村の役所 |
| 公社 | 特定の事業を運営させるために国や地方公共団体が設立した法人 (例)公益社団法人・公益財団法人・独立行政法人 |
| 機構 | 特定の事業を運営させるために国が設立した法人 (例)独立行政法人 |
特に官公庁は、公共工事を発注する立場として有名です。
発注者の仕事に興味関心がある方は、チェックしてみると良いでしょう。
ゼネコン
「ゼネコン」は、ゼネラルコントラクターの略です。
ゼネラルコントラクターを日本語に直すと、総合建設業者。
建設プロジェクトの「施工」を行っているのがゼネコンです。
建設業では、ゼネコンを「大手」「準大手」「中堅」と呼ぶことも多く、特定の工事に強みを持っている企業もあります。
ゼネコンに就職することで、大規模な建設プロジェクトに参加できるのが魅力です。
ただし、ゼネコンは日本全国へ転勤の可能性もあります。
一方で地場コンと呼ばれる地場ゼネコンは、地元に密着して建設工事を行う企業です。
地場コンはゼネコンに比べて転勤が少ないため、地元や特定の地域で仕事をすることも多い傾向があります。
ゼネコンといっても、企業ごとに強みが異なります。
たとえば、橋梁工事をやりたい場合は、橋梁工事の施工実績があるかもチェックしましょう。
建設コンサルタント
「建設コンサルタント」は、調査・計画・設計などの建設コンサルタント業務を担当します。
また、発注者をサポートし建設プロジェクトを推進する技術者集団です。
建設コンサルタントは、施工管理や維持管理や点検を行うなど、建設プロジェクトの一連の流れに関われます。
建設コンサルタント業務では建設に関する高い専門知識が必要となるので、技術者にとってもっとも権威のある「技術士」の資格保有者が多いのも特徴です。
建設コンサルタント業務には、以下のとおり21の分野があります。
- 河川、砂防及び海岸・海洋
- 港湾及び空港
- 電力土木
- 道路
- 鉄道
- 上水道及び工業用水道
- 下水道
- 農業土木
- 森林土木
- 造園
- 都市計画及び地方計画
- 地質
- 土質及び基礎
- 鋼構造及びコンクリート
- トンネル
- 施工計画、施工設備及び積算
- 建設環境
- 機械
- 水産土木
- 電気電子
- 廃棄物
- 建設情報
建設コンサルタントといっても、企業ごとに強みを持つ分野が異なります。
企業のコーポレートサイトや採用案内のパンフレットなどで、企業ごとに強みを持つ分野を明確にしておきましょう。
参照:一般社団法人 建設コンサルタンツ協会|建設コンサルタントとは
以下記事では、建設コンサルタントの仕事内容について解説しています。
建設コンサルタントの魅力、きつい点についても紹介しているので、あわせてご覧ください。

道路
建設プロジェクトの中でも、道路を専門としている企業もあります。
たとえば、高速道路の管理を行なっている代表的な企業といえば、NEXCO各社です。
NEXCO各社とは「東日本高速道路株式会社」「中日本高速道路株式会社 」「西日本高速道路株式会社」の3社を指します。
人々が安心して高速道路を利用できるように、NEXCO各社では新設・改築・維持・修繕を行っています。
床版取替などのリニューアル工事を進めているのも特徴です。
NEXCO各社以外にも「首都高速道路株式会社」「阪神高速道路株式会社」「本州四国連絡高速道路株式会社」など、高速道路を管理している企業があります。
また、高速道路をはじめとする道路の舗装工事、空港の滑走路の整備などを専門に工事をしている企業もあります。
中でも有名なのが「株式会社 NIPPO」「前田道路株式会社」「日本道路株式会社」などです。
ただし、道路工事を行う場合は通行止めをする必要があるため、夜間に仕事をすることも増えます。
筆者も、道路工事をするために何度か夜間作業を経験しました。
夏の夜間工事は暑さを感じにくいというメリットがありつつも、生活リズムが慣れるまでに苦労した経験があります。
このように、道路工事は夜間作業もあるという点を押さえておきましょう。
鉄道
鉄道に関する建設プロジェクトに強みを持つ企業もあります。
駅や周辺の整備、高架化や改良なども実施しています。
代表的なのがJR各社です。
JR各社には「東日本旅客鉄道株式会社」「東海旅客鉄道株式会社」「西日本旅客鉄道株式会社」などがあります。
ほかにも「東武鉄道株式会社」「京浜急行電鉄株式会社」「阪急電鉄株式会社」など、民営鉄道(私鉄)もあります。
駅周辺工事は昼間に実施されるのが多い一方で、鉄道の軌道工事は時間の制約が厳しいのが特徴です。
軌道工事の作業を始められるのは、終電が通過してから始発が発車する前までの時間です。
ほかの建設工事に比べて、軌道工事は綿密なスケジュールを立てて作業を進めなければなりません。
軌道工事の担当になると、終電が通過してから始発が発車する前に仕事をするため、必然的に夜間作業となります。
不動産・住宅
土木工学を専攻した学生の就職先として、不動産・住宅も挙げられます。
土木工学には「都市計画」「交通」「構造」「地盤」「水工」など、さまざまな専門分野があります。
都市計画に興味がある方は、不動産デベロッパーなどに就職することも。
不動産デベロッパーとは、都市開発など街全体の開発事業を行う企業です。
代表的な不動産デベロッパーには「三井不動産株式会社」「三菱地所株式会社」「住友不動産株式会社」などがあります。
また、土木工学で学びを深めるうちに、建築に興味を持つこともあるでしょう。
住宅の設計・施工に関わりたい場合は、ハウスメーカーや工務店などを選ぶのも1つの方法です。
情報・通信
建設業の中でも、情報・通信に関する企業を選ぶ人もいます。
国土交通省をはじめ、建設業では生産性向上や省人化などの取り組みが進められています。
建設業に特化したSaaSやアプリケーションを提供している企業も増えてきました。
建設業が抱える課題を解決する手段として、今後も情報・通信の分野は注目されるでしょう。
ただし、情報・通信へ就職すると、ITスキルが求められることもあります。
土木工学の基礎知識以外に、ITスキルを身につける必要がある点を理解しておきましょう。
メーカー
建設業に就職する際、メーカーを選ぶ方もいます。
土木工学を学べる学科では、コンクリートなど材料工学に関して履修することもあるでしょう。
コンクリートといえば、骨材(粗骨材・細骨材)・水・セメント・混和材料でできています。
そしてコンクリートは、さまざまな建設現場で使われています。
そんなコンクリートを構成するセメントを製造するメーカー、プレキャスト製品を製造するメーカーもあります。
プレキャスト製品とは、現場でコンクリートの打ち込みをせず、あらかじめ工場などで製造されたコンクリート部材です。
筆者の周りでも、コンクリートの研究室で卒業研究をした後、メーカーへ就職した方がいました。
コンクリートに関して興味関心がある方は、メーカーも就職先の選択肢といえます。
建設業に就職するときのチェックポイント7選

建設業に就職するときのチェックポイントは、以下の7つです。
筆者も就職活動前に十分に事前準備ができていなかったので、就職活動の真っ只中に悩むことも多くありました。
就職活動の不安を少しでも減らすためにも、ぜひ参考にしてみてください。
将来のキャリアプランを立てる
建設業に就職するときは、将来のキャリアプランを立てることが重要です。
これから社会人となる学生にとっては、キャリアプランといわれてもイメージがつかないかもしれません。
ただ、1年後・3年後・5年後の将来像を明確にすることで、就職先とのミスマッチを防ぐことにもつながります。
自分のキャリアプランが曖昧だと、入社後に「こんなはずではなかった」と後悔することもあるでしょう。
キャリアプランを考える際、まずは中長期的な大きな目標を考えるのがおすすめです。
たとえば「5年後には施工管理技士の資格を取得する」「10年後には優良工事の表彰をもらう」などが、中長期的な大きな目標の一例です。
大きな目標を達成するために何をやるべきかなど、短期的な目標を具体例として考えておくと、キャリアプランを立てやすくなります。
企業選びで優先することを明確にする
建設業に就職するときは、企業選びで優先することを明確にしましょう。
就職先を選ぶポイントは、人によって異なります。
以下は、就職先を選ぶポイントの一例です。
【就職先を選ぶポイント】
- 事業内容
- 企業理念
- 社風
- 将来性
- 働きやすさ
- 勤務地
- 給与
- 福利厚生
- 社員研修の充実度
- 女性社員がいるか
上記は一例ですが、仕事をする際に優先度を決めることが大切です。
すべて自分が納得できればベストですが、必ずしも希望通りにならないこともあります。
企業選びの優先度を決めずに就職活動をしてしまうと、以下のようにどの企業に入社するか迷ってしまうことも。
「事業内容に魅力を感じているけど、全国転勤があるから嫌だな」
「転勤がなく自宅から通勤できるけど、事業内容が希望と違う」
事業内容と勤務地のどちらを優先するかによって、就職先が変わることが十分あるでしょう。
特に、女性の場合は「女性社員がいるか」も重要ポイントです。
すでに女性が活躍している企業に入社すると、働きやすい労働環境が整っている可能性が高いといえるでしょう。
以下記事では、建設業での女性就業の定着促進の紹介しています。
建設業における女性にオススメの職種も紹介しているので、チェックしてみてください。

資格取得など支援制度が充実しているかを確認する
建設業に就職するときは、資格取得など支援制度が充実している企業かを確認しましょう。
建設業で活躍する上で、資格の取得を目指す方も多いでしょう。
代表的な資格といえば、技術士・施工管理技士(1級・2級)・RCCM・コンクリート診断士・測量士などです。
資格の難易度にもよりますが、独学だけでは合格が難しいこともあります。
たとえば、施工管理技士試験の第二次検定では、実務経験に関する記述問題が出題されます。
すでに施工管理技士の資格を保有している先輩や上司などがいれば、記述問題を添削してもらえるでしょう。
筆者も、上司と二人三脚で一級土木施工管理技士の資格を取得できました。
わからないところを何度もイラストで教えてもらえたので、理解度も進んでいるように感じました。
いち早く資格を取得し活躍するためにも、企業選びの際は資格取得など支援制度が充実している企業かをチェックしましょう。
当社MACでは、資格取得支援制度に力を入れています。
受験費用や学習費用の補助をしているほか、合格祝金として最大10万円を支給。
当社では、資格取得を徹底してサポートする環境が整っています。
当社の資格取得支援制度について詳しく知りたい方は、以下リンクよりご確認ください。
労働環境が整っているかを確認する
建設業に就職するときは、労働環境が整っているかを必ず確認しましょう。
たとえば「時間外労働を含めた労働時間はどのくらいか」や「指導してくれる先輩や上司との距離感は近いか」などです。
労働環境が整っていないと、ストレスを抱えたりミスが増えたりするなど、仕事で成果を出しにくくなります。
また、会社内に女性技術者が1人もいない場合は、まだ女性が安心して仕事ができる労働環境が整っていない可能性も。
ライフスタイルの変化にあわせて働き方を変えられるかなども、企業選びをする上で重要なポイントです。
企業のコーポレートサイトを確認し、労働環境について不安点をなくしておきましょう。
ただし、コーポレートサイトだけでは、疑問点が解決できないこともあります。
会社説明会では、採用担当者に質問する機会もあることが多いので、採用担当者に疑問点を質問し解消しておくと安心です。
企業研究を怠らない
建設業に就職するときは、企業研究を怠らないようにしましょう。
十分に企業研究をせずに選考に進み入社してしまうと、後々「自分が思っていた仕事と違う」と後悔することもあります。
また、企業規模や知名度だけで就職先を選んでしまうと、企業の事業内容と自分がやりたいことにミスマッチが起こり、やりがいを感じられないこともあるでしょう。
さらに、同じ企業希望や知名度だとしても、企業ごとに独自の強みは異なります。
「橋梁の工事がやりたかったのに、トンネルの工事を担当することになった」
「施工管理の仕事がしたかったのに、設計の仕事をやることになった」
このように、自分の希望とかけ離れた仕事を続けるのは難しいですよね。
すべて自分の希望通りにならないこともありますが、将来的に希望の仕事ができるかどうかを知るためにも、企業研究は重要です。
企業研究の際は企業の採用案内はもちろん、コーポレートサイトに掲載しているIR情報を活用するのもおすすめです。
IR情報は、株主や投資家向けに情報提供をしているので、企業の経営状況や今後の経営計画などを把握でき、キャリアプランを立てやすくなります。
会社説明会やOB・OG訪問などを利用する
建設業に就職するなら、会社説明会やOB・OG訪問などを利用すると良いでしょう。
企業のコーポレートサイトや採用案内でも情報収集はできますが、知りたい情報をすべて把握するのは難しいでしょう。
会社説明会に参加すれば、企業の採用担当者が詳しく会社に関しての説明をしてくれるので、事業内容・社風・社員の雰囲気などを理解しやすいのが特徴です。
さらに、チャンスがあればOB・OG訪問をしてみましょう。
OB・OG訪問をすると、企業に所属する母校の卒業生に会って直接話ができます。
特に給与や賞与の話などは、採用担当者にはなかなか相談できないですよね。
OB・OG訪問では、採用担当者に話しにくい内容をすべて打ち明けてみましょう。
筆者が就職活動をしていたときも、OB・OGを頼っていました。
建設現場に少しずつ女性技術者が増えてきた頃に就職活動をしていたので、女性が活躍できるのかどうかが気になっていました。
「社内に技術職の女性はどのくらいいるか」
「施工管理をやりたいけど、現場の雰囲気はどうか」
このように、母校のOB・OGに相談したので、入社後のイメージもしやすかったように感じます。
選考に進みたい企業にOB・OGがいるかわからない場合は、大学のキャリアセンターや研究室の教授に聞いてみると教えてもらえるでしょう。
会社見学や現場見学があれば参加する
会社見学や現場見学があれば、できるだけ参加することをおすすめします。
会社見学をすると、実際に仕事をしている社員の雰囲気、社員同士の距離感などを感じられます。
筆者が就職活動をしているときも何度かオフィス内を見学したので、会社説明会だけでは伝わらない社員の雰囲気を感じることができました。
また、就職活動をしている学生向けに、現場見学会を実施している企業もあります。
大学で土木工学を学ぶ際、知識の習得は座学がメインかもしれません。
筆者は、土木工学の基礎知識は座学で学び、実習や実験などを数回経験した程度です。
施工管理を希望していましたが、大学時代は数回しか建設現場に行ったことがありませんでした。
施工管理の仕事を詳しく知りたかったので、就職活動時は企業が開催する現場見学会に参加し、橋梁工事・道路工事を見学しました。
大学の授業で学んだ内容は、現場でどのように使われているのかなど、座学ではわからないことが現場には詰まっています。
また、建設工事のダイナミックさや魅力に浸れる場所でもあるので、ぜひ参加してみてください。
建設業界への就職ならMACにご相談ください

今回は、建設業に就職を決めた理由をご紹介しました。
建設業の主な就職先、就職活動時にチェックするポイントも解説したので、就職活動の不安が払拭されれば幸いです。
「建設業に就職して後悔しないか」
「建設業で長く仕事を続けられるか」
このように、はじめての就職活動では不安を抱えてしまうこともありますよね。
本記事は、社会人となった今の筆者から、就職活動をしていた頃の大学生の筆者に伝えたいことを盛り込んだ内容です。
後悔しない就職活動をするためにも、事前にできることから準備を始めていきましょう。
「建設業への就職を決めてよかった」
土木工学を学んできた皆さんから、このような声が聞けるのを楽しみにしています。
当社MACでは、建設業のご紹介・案内を行っております。
以下のLINEから無料で就職・転職相談が可能なので、お気軽にお問い合わせください。