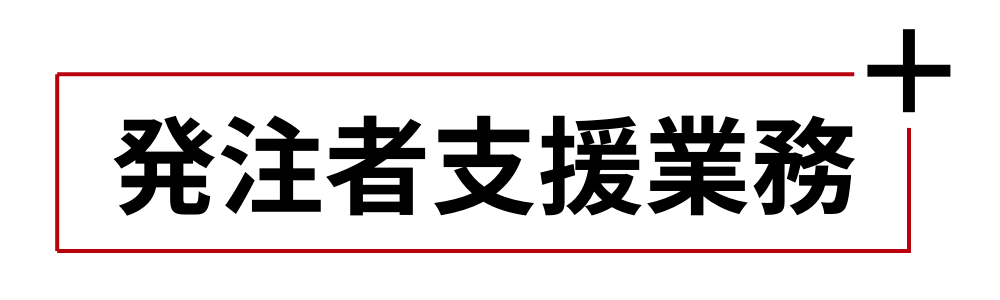「学生時代に学んだ土木の授業、正直ほとんど覚えていない…」
「授業内容を忘れていても、土木の仕事ってできるの?」
そんな不安を抱えて、就職活動を始める方もいるかもしれません。
測量学・構造力学・地盤力学・水理学・コンクリート工学など、学生時代にはさまざまな専門科目を学びます。
とはいえ、すべてを完璧に理解して卒業できる学生は、実はほんの一握り。
筆者自身も、内容を理解しないまま単位を取った授業、すっかり忘れてしまった知識がたくさんありました。
それでも企業から内定をいただき、現場技術者として日本全国の土木工事に9年間関わることができました。
この記事では、土木の授業内容をすべて覚えていなくても問題ない理由を、筆者の実体験を交えてお伝えします。
“知識が足りないかも…”と不安を感じている方の背中を、少しでも押せたら幸いです。
- 就職活動で出会う就活生が抱える悩み
- 現場で求められるのは知識よりも対応力
- 知識不足を強みに変えられた筆者のエピソード
当社MACでは、建設業のご紹介・案内を行っております。
以下のLINEから無料で就職・転職相談が可能なので、お気軽にお問い合わせください。
“授業覚えてない…”はあなただけじゃない!みんな不安だった就活の話

「授業の内容を忘れていたら、企業から内定はもらえないの?」
「正直、1年生の頃に習った内容なんて覚えていないんだけど…」
筆者が就職活動を始める前、学科の友人と話していました。
当時、筆者も授業の内容を完璧に理解しておらず、土木の知識不足に不安を感じていました。
就職活動がスタートすると会社説明会にも足を運びましたが、ほかの学生からも同じ質問が挙がっていたのを覚えています。
「当社の会社説明会は以上で終了です!何か質問はありますか?」と、企業の採用担当者が話したときに、学生の一人が不安そうに小さな声で質問したことは…
「大学で学んだ内容を忘れてしまったのですが…現場の仕事ってできますか?」
このような声から、学生の多くが土木の知識不足に不安を感じているのだとわかりました。
たしかに、土木に関して多くの知識を習得している方が望ましいでしょう。
しかし、高校受験や大学受験と同じように、すべての知識を100%習得することは難しいものです。
ある企業の選考の筆記試験では、技術士の第一次試験(専門科目)で出題される問題を解きました。
「これでは面接に進めないだろう」と感じるほど自信がありませんでしたが、後で聞いたところ”参考程度”としていたようです。
面接で土木に関する知識を問われたことはなく、上記の一度きりです。
建設業界の採用担当者と話したときも、”入社してから実務で学べばいい”と聞くことも多いため、知識不足に関して深く悩む必要はないでしょう。

現場では「知識」よりも「対応力」が大事

現場技術者として仕事をするときに求められるのは「知識」よりも「対応力」です。
土木のどの分野を専門に学んだか、学部卒なのか大学院卒なのかなど、実務にほとんど影響しません。
現場では、誰でも同じスタートラインに立てるということです。
ここからは、筆者の経験・体験を交えて対応力が大切な理由をお伝えします。
現場では“その場で調べる力”が武器になる
現場では、わからないことを調べる力が武器になることもあります。
たとえば、現場の仕事の一つが品質管理。
コンクリート構造物を例に考えてみましょう。
コンクリート構造物が発注図面通りに施工されているか、コンクリート構造物の幅・高さ・延長は規格値に収まっているかなど、施工管理要領に基づいて品質管理を行います。
施工管理要領は発注者ごと、どの項目を・どのくらいの頻度で・どのように試験を実施するかなどが異なります。
品質管理を行うためには、施工管理要領に記載されている内容を把握しなければなりません。
ただ、現場経験が豊富な上司や先輩でも、施工管理要領の中身を一字一句まで理解しているわけではありません。
つまり、新入社員でも調べる力があれば、業務をスムーズに進められる可能性はあります。
はじめは、施工管理要領から該当箇所を見つけるのに苦戦するかもしれませんが、独自のシートなどを作成して管理すれば、その場ですぐに質問に回答ができるでしょう。
わからないことがあったら、まずは自分なりに調べることから始めることが大切です。
基礎知識は、実務とセットで定着していく
土木に関する基礎知識は、机上でなく実務とセットで定着していきます。
筆者は、大学3年生のときに”RC構造デザイン実習”という授業を受講しました。
橋梁下部工の設計計算を行った後、CADツールを使って図面を作成し、最後に模型を制作するという授業です。
当時は、鉄筋の”かぶり”や”空き”のイメージがわかないまま、模型制作に取り組み単位を取得したので、RC構造について理解度が低いまま入社したのが本音です。
しかし、現場で職人さんたちが鉄筋を組み立てる様子を間近で見たことで、すぐに鉄筋の”かぶり”や”空き”の違いを理解できました。
2次元で図面を作成するときに一本線で表示される鉄筋。
ただ、実際には鉄筋は厚みを考慮し、かぶりや空きを確保していることもわかりました。
このように、実際の現場で経験・体験を積み重ねることで、机上では理解できなかった知識を習得しやすくなります。
現場で職人さんの作業を間近で見たり、上司や先輩に質問したりするなど、積極的に基礎知識を吸収する行動を取れば、土木の知識不足をカバーできることもあります。
実務をこなしながら一つずつ覚えていきましょう。
「覚えていない」「苦手だった」からこそ強みになることもある

「授業の内容を覚えていない」「土木の〇〇の分野が苦手…」
このような土木の知識に関する不安が、逆に強みになることもあります。
現場の仕事を始めた当時の筆者は、構造力学の初歩的な知識を理解していた程度です。
ただ、土木の知識不足を感じているからこそ、実務への向き合い方が変わったと思っています。
ここからは、土木の知識不足が強みに変わった具体的なエピソードを紹介します。
調べ癖がつきミスを防止できる
土木に関する知識不足を感じている新入社員だからこそ、調べ癖がつきミスの防止に貢献できます。
授業で学んだ内容を覚えていなかったり、苦手だと感じていたりすると、実務を進める中で何かと調べる時間が増えるでしょう。
調べる力は、根拠を探すときにも欠かせないため、中長期的に見ても自分の強みになります。
筆者も、仕様書や設計・施工指針などの専門図書を探し回り、数百ページの中から該当箇所を見つけ出したことが何度もあります。
一方で上司や先輩は、経験則に基づいて行動することが増えますが、稀に思い込みなどでミスをすることも。
上司や先輩、協力会社や発注者のミスを指摘するときに根拠を提示できるので、説得力が増し信頼してもらえるきっかけにもなります。
また、専門図書などの書籍だけでなく、ベテラン技術者などの経験者に質問するのもおすすめです。
業務を進める過程でミスをした場合は、同じミスを繰り返さないようにノートにまとめるのも良いでしょう。
部下や後輩の育成に役立つ
覚えていないことや苦手なことがあるからこそ、自分の力で調べたり経験・体験をしたりするため、数年後に部下や後輩を育成するときに役立つでしょう。
「自分が理解したことや経験したことでなければ、人に語ることはできない」
この言葉は、筆者が尊敬する上司がよく話していたことで、今でも筆者が大切にしている考え方です。
筆者に部下や後輩がいたことはありませんが、同僚への説明で自分が調べた経験・体験が役立ちました。
発注者から指摘があったときの根拠資料、職人さんとの打ち合わせで必ず話すべき内容など、類似工事を経験する同僚へ先回りして説明ができたこともあります。
わからないことを自力で調べて説明しても相手が納得してくれないとき、心が折れそうな辛い思いをすることでしょう。
しかし、苦労や葛藤は無駄にはならず、教える側になったときに必ず役立ちます。
「自信がないまま就職」はダメじゃない

「土木の知識を完璧に覚えていないから、現場の仕事は無理かも…」
そう思っているあなたへ伝えたいことは、自信がないまま就職しても問題ないということです。
たとえ土木の基礎知識を忘れてしまっても、建設現場には成長できる環境があります。
なぜ、自信がないまま就職しても大丈夫なのか、知識不足のまま就職活動に挑んだ筆者の経験談をシェアします。
“何もかも理解してから”じゃなくていい
土木の知識を100%理解できていなくても、現場の仕事はできます。
何もかも理解してからじゃないといけないと考える必要はありません。
筆者は、大学2年生の頃にコンクリート工学という必修科目を履修しましたが、試験を受けると合格点に到達できず再履修することになった経験があります。
大学4年生の頃は都市計画系の研究室に配属したので、採用面接で出会った学生の誰よりも専門知識の理解度が低かったかもしれません。
ただ、入社後は先輩や上司と一緒に実務経験を積むうちに、少しずつ知識が身につきました。
今、もし土木の知識不足に不安を感じていても、入社後に一つずつ学んでいけば問題ありません。
できないところから一緒に育ててくれる現場がある
「土木の知識は、自分一人で身につけなければいけないの?」
このように不安を感じている方へ伝えたいことは、できないところから一緒に育ててくれる現場があるということです。
一昔前は、上司や先輩の仕事をみて、真似をするように実践するのが一般的だったと聞きます。
しかし、筆者が現場の仕事を始めた頃は、すでに指導の仕方が想像していたものと違いました。
上司や先輩が筆者の隣で説明しながら実践し、目線を下げて指導してくれました。
現場では、部下や後輩の育成もチーム戦です。
新入社員に寄り添って、根気強く親身になって育ててくれる環境があります。
土木は知識習得に終わりはない
”土木は経験工学”と呼ばれるように、経験から学べることも多いのが現場の仕事です。
さらに、土木の知識習得に終わりはありません。
現場の仕事に関われば、新入社員に限らず全員が学びの連続です。
実は、新入社員や若手社員の指導をしている上司や先輩にもわからないことがあります。
「どうして上司は何を聞かれても答えられるのだろう」
「発注者にも職人さんにも、あんなに自信を持って話せるなんて…」
発注者や職人さんへの上司の対応力にかっこいいと思いつつも、自分との大きな差を感じ肩を落としたことがあります。
ただ、そんな上司も筆者と同じように、わからないことを抱えながら仕事をしていました。
勤続年数が長い社員であっても、新入社員と同じように学びと実践を繰り返して今があるのです。
今、もし土木の知識不足に不安を感じている方は、気持ちが少し楽になったのではないでしょうか?
どんなに大学で学んだ内容を理解していても、100%習得し切るのが難しいのが土木。
土木の知識習得に終わりはないからこそ、わからないことに対して落胆することなく、新しいことを覚えることを素直に楽しむことも大切です。
建設業界への就職ならMACにご相談ください
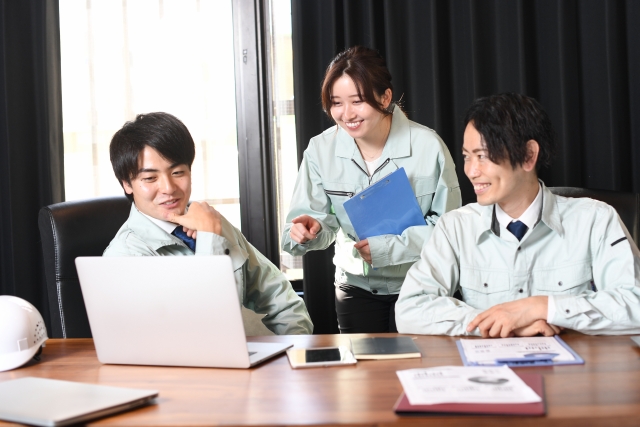
今回は、授業で学んだ内容を覚えていなくても現場の仕事ができることを、筆者のエピソードを交えて解説しました。
就職活動を始める前は、さまざまな不安を抱えますよね。
筆者も「土木技術者として仕事をするのに、採用面接で土木の基礎知識を問われたらどうしよう」と不安を感じ、怯えながら面接に挑んでいました。
現場の仕事では数学や物理の知識を必要とすることもありますが、わからないことがあっても一から吸収すれば問題ありません。
「あれ?この分野、大学で学んでこなかったの?」と、上司や先輩から聞かれたことがあります。
「学んだはずですが、忘れたので教えてください!」と、筆者は知ったかぶりをせずに質問することを心がけていましたが、素直に聞くことが大切だと思っています。
土木の知識不足を理由に、現場の仕事を諦める必要はありません。
学生時代に学んだ土木の知識を復習するつもりで、現場の仕事に向き合ってみてくださいね。
当社MACでは、建設業のご紹介・案内を行っております。
以下のLINEから無料で就職・転職相談が可能なので、お気軽にお問い合わせください。