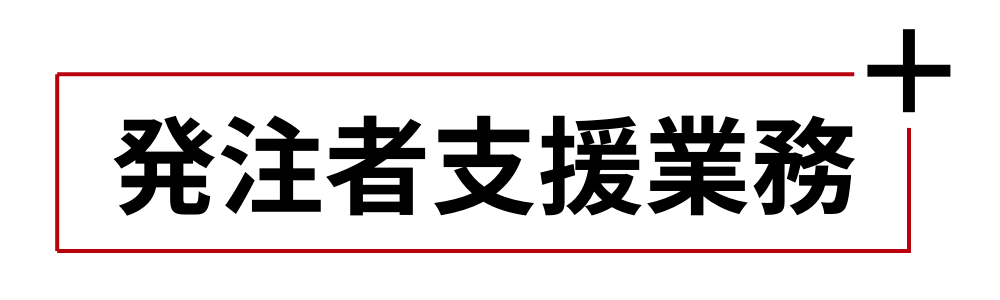建築施工管理技士には1級と2級がありますが、1級の主な仕事内容や試験の概要をご存知でしょうか?
今回は、1級建築施工管理技士についてわかりやすく解説します。
また、取得したほうが良い理由や合格する方法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 1級建築施工管理技士の主な仕事内容
- 1級建築施工管理技士の試験概要
- 1級建築施工管理技士に合格する方法
MACは、建設業界への転職を支援しています。
多数の求人を取り扱っているため、建設業界への転職に興味のある方は資格の有無にかかわらず、お気軽にご相談ください。
1級建築施工管理技士とは?主な仕事内容を紹介

1級建築施工管理技士は、国家試験の一つである施工管理技術検定に合格した方のことです。
例えば、建築工事の施工計画を作成したり、現場での工程管理を行ったりします。
また、1級建築施工管理技士は請け負う工事の規模に限度がないので、規模の大きい現場にも携わることができます。
1級建築施工管理技士の詳細は、以下の記事でも確認してみてください。

【試験概要】1級建築施工管理技士になるには?

では、1級建築施工管理技士になるにはどうすればいいのでしょうか?
ここで、受験資格や手数料などを確認しておきましょう。
受験資格
受験資格は、第一次検定と第二次検定で異なります。
第一次検定は、試験が行われる年度に19歳以上になる方が対象です。
一方第二次検定は、受験資格が細かく設定されています。
| 種類 | 条件 |
|---|---|
| 1級第一次検定合格者 | ・実務経験5年以上 ・実務経験3年以上(特定実務経験1年以上を含む) ・監理技術者補佐として実務経験1年以上 ※いずれも1級建築施工管理技士の第一次検定合格後 |
| 1級第一次検定・2級第二次検定合格者 | ・実務経験5年以上 ・実務経験3年以上(特定実務経験1年以上を含む) ※いずれも2級建築施工管理技士の第二次検定合格後 |
| 1級第一次検定受験予定・2級第二次検定合格者 | |
| 1級建築士試験合格者 | ・実務経験5年以上 ・実務経験3年以上(特定実務経験1年以上を含む) ※いずれも1級建築施工管理技士の第一次検定合格後 |
ただし、受験資格は変更されることもあるため、検定を受けるまでは必ず「受験の手引」を確認しましょう。
受験手数料・試験地
受験手数料は、第一次検定・第二次検定ともに1万2,300円(非課税)です。
一次・二次両方受験する場合は、第二次検定の受験手数料を第一次検定合格後に支払うことになります。
また、試験地は以下のとおりです。
- 札幌
- 仙台
- 東京
- 新潟
- 名古屋
- 大阪
- 広島
- 高松
- 福岡
- 沖縄
ただし、会場の都合でその他の都道府県などで実施されることもあるため、試験地については事前に確認しておきましょう。
合格率
1級建築施工管理技士の合格率は、以下のとおりです。
| 年 | 第一次検定 | 第二次検定 |
|---|---|---|
| 2022年 | 46.8% | 45.2% |
| 2023年 | 41.6% | 45.5% |
| 2024年 | 36.2% | 40.8% |
一次・二次いずれも直近の合格率が低下していますが、40%前後と考えておいて問題はないでしょう。
ただし、合格率だけ見ると検定が難化しているようにも捉えられます。
そのため、4割程度合格するからといって油断するのは禁物です。
1級建築施工管理技士はすごい?取得したほうが良い理由

1級建築施工管理技士を取得したほうが良い理由は、以下のとおりです。
- 現場での対応力が向上する
- 監理技術者・主任技術者として働ける
- 経営事項審査で有利になる
取得することを迷っている方は、メリットも踏まえて判断してみてください。
現場での対応力が向上する
1級建築施工管理技士を取得すると、現場での対応力が向上します。
1級建築施工管理技士は、簡単に合格できる検定ではありません。
そのため、現場だけではなくテキストなども使ってしっかり知識を蓄えます。
検定に合格できるほどの知識があれば、現場での対応力も自然に向上するでしょう。
監理技術者・主任技術者として働ける
1級建築施工管理技士を取得すれば、監理技術者・主任技術者として働けます。
特に、監理技術者は下請契約の請負代金総額が4,500万円以上の場合、現場に専任で配置しなければなりません。
つまり、企業にとってより重要な人材になれます。そのため、しっかりと経験を積めるだけではなく、給料アップにもつながるでしょう。
経営事項審査で有利になる
職場に監理技術者がいると、経営事項審査で有利になります。
そのため、監理技術者になれる1級建築施工管理技士は非常に重宝されるでしょう。
企業からも求められる人材になれるため、結果として転職やキャリアアップに役立ちます。
1級建築施工管理技士の受験資格は変更された
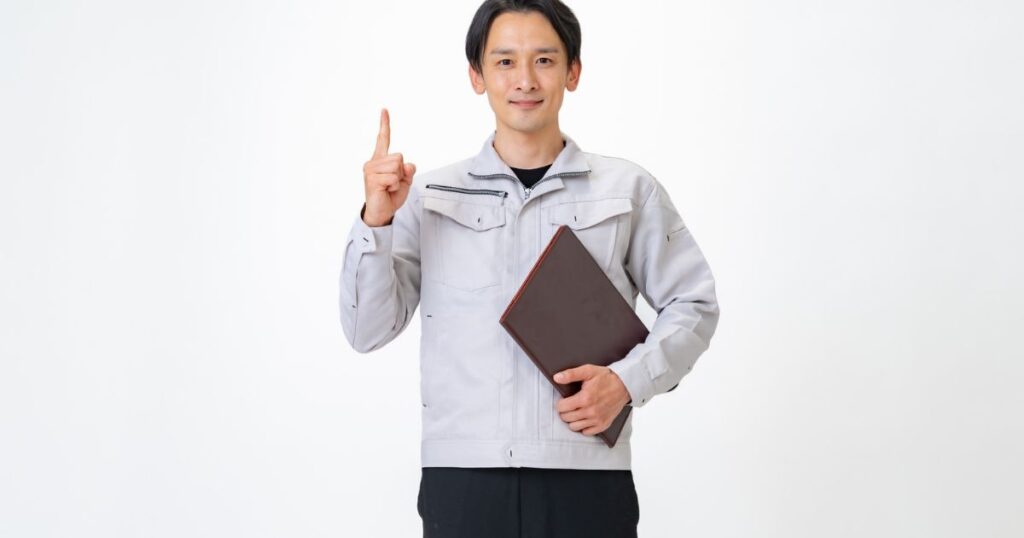
実は、1級建築施工管理技士の受験資格は2024年度の試験から変更されています。
従来は、第一次検定の受験資格として実務経験が必要でした。
しかし、2024年度の試験より第一次検定の受験資格から実務経験がなくなりました。そのかわりに、年齢制限が設けられています。
現在、1級建築施工管理技士の第一次検定は、試験実施年に19歳になる方であれば誰でも受験できます。
ただし、第二次検定では実務経験が必要となるため、混同しないように注意しましょう。
1級建築施工管理技士に合格する方法

1級建築施工管理技士に合格するためには、以下のことを意識しましょう。
- 計画を立てて学習を進める
- 問題を解くだけではなく解説も読み込む
- スキマ時間を活用する
- 必要に応じて通信講座を検討する
最短で合格したいと考える方は、ぜひ参考にしてみてください。
計画を立てて学習を進める
1級建築施工管理技士に合格したいなら、計画を立てて学習を進める必要があります。
特に、仕事をしながら学習を進める場合はスケジューリングが非常に重要です。
まずは試験日を確認し、無理のない学習計画を立てましょう。
急な残業や休日出勤も想定して、余裕を持った学習計画を立てておくのがおすすめです。
問題を解くだけではなく解説も読み込む
学習を進めていると、問題を解く場面も増えてきます。ここで、単に問題を解いているだけだと合格率は上がりません。
なぜなら、なんとなく選んだ回答がたまたま正解していることもあるからです。
正確に理解できていないまま学習を進めると、本番でミスしてしまう恐れがあります。
問題を解く際は、解説まで読み込むことを癖づけておきましょう。
スキマ時間を活用する
1級建築施工管理技士に合格したいなら、スキマ時間も有効活用しましょう。
通勤時間や昼休憩など、少しでも時間が確保できるのであれば学習を進めることをおすすめします。
1回15分でも、4回繰り返せば1時間です。スキマ時間でやることをあらかじめ決めておくとスムーズに学習に入れます。
ぜひ試してみてください。
必要に応じて通信講座を検討する
「一人で学習を進めるのが苦手」「最短で合格したい」と考える方は、必要に応じて通信講座を検討するのも一つの手です。
通信講座は、学習計画を提案してくれたり、頻出度の高い重要な内容をピックアップしてくれたりするため、効率よく学習を進められます。
費用はかかりますが、不合格になって何度も受験するよりはいいかもしれません。
なお、MACでは「資格取得支援制度」を実施しております。
最大10万円の合格祝金をご用意しているので、詳細をぜひ以下のリンクでチェックしてみてください。
1級建築施工管理技士と2級の違い

1級と2級では、管理できる現場の規模が異なります。
例えば、1級建築施工管理技士は現場の規模に上限がないので、大規模な工事も担当可能です。
一方2級建築施工管理技士は、中小規模の工事を担当します。
また、2級建築施工管理技士は資格が以下の3つの区分に分かれており、管理できる工事内容が異なるため、注意が必要です。
- 建築
- 躯体
- 仕上げ
1級建築施工管理技士は制限がない、2級は一部制限があると覚えておくとよいでしょう。
1級建築施工管理技士はすごい資格!

1級建築施工管理技士は、取得すれば監理技術者として働けるようになり、企業からも非常に重宝される人材になれます。
しかし、計画なしに学習を進めているとなかなか合格できない恐れがあります。
しっかり学習計画を立て、スキマ時間を有効活用しましょう。必要に応じて通信講座を利用するのも一つの手です。
また、転職を検討している方は学習と並行して求人を探してみてください。
実は、1級建築施工管理技士の資格がなくても転職できる優良求人はいくつもあります。
合格するまで待っていると転職のタイミングを逃す恐れもあるため、同時並行で進めるのがおすすめです。
建設業界への転職については、求人を多く取り扱っているMACにお気軽にご相談ください。