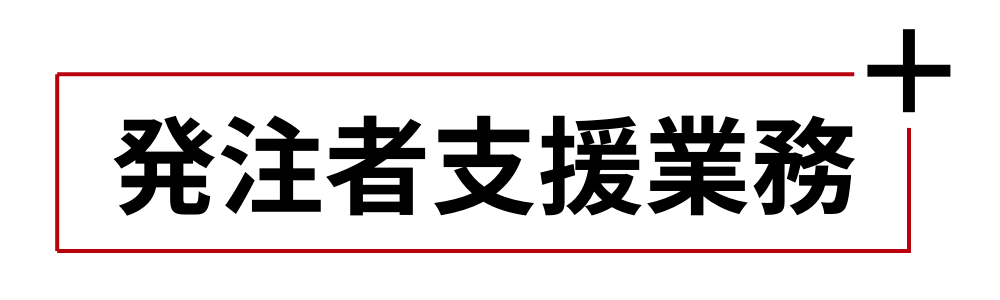建築施工管理技士には1級と2級がありますが、みなさんに質問です。
- 2級建築施工管理技士は何ができる?
- 受験資格は?
- 2級を取得するメリットはある?
わからない部分があった方は、ぜひこの記事を最後まで読んでみてください。
本記事では、2級建築施工管理技士には何ができるのか、検定概要、取得後のメリットなどをわかりやすく解説します。
- 2級建築施工管理技士とは
- 検定概要
- 合格に必要な勉強時間
私たちMACは、建設業界への転職をサポートしています。
建設業界に興味がある方は資格の有無にかかわらず、ぜひお気軽にお問い合わせください。
2級建築施工管理技士とは?できることを紹介

2級建築施工管理技士は建設業法に基づく国家資格の一つで、以下の3つの区分があります。
- 建築
- 躯体
- 仕上げ
具体的には、工事の工程表といった資料の作成や品質管理などの業務を担当します。さらに、建設現場において安全管理も担当するため、非常に重要な仕事です。
また、2級建築施工管理技士になると、建設現場に配置する主任技術者になれます。
以下の記事も併せて参考にしてみてください。

2級建築施工管理技士になるには受験が必要

では、2級建築施工管理技士になるにはどうすればいいのでしょうか?
結論をお伝えすると「2級建築施工管理技術検定」に合格する必要があります。
そこで、2級建築施工管理技術検定の受験資格や合格率などを確認しましょう。
受験資格
2級建築施工管理技士の検定は第一次検定と第二次検定に分かれており、それぞれ受験資格が異なります。
| 検定 | 受験資格 | |
|---|---|---|
| 第一次検定 | 試験実施年度に満17歳以上 | |
| 第二次検定 | 区分1 | 2級の第一次検定合格後、実務経験3年以上 |
| 区分2 | 1級の第一次検定合格後、実務経験1年以上 | |
| 区分3 | 1級建築士試験に合格したあと、実務経験1年以上 | |
例えば、令和7年度に第一次検定を申し込むなら生年月日が平成21年4月1日以前である必要があります。
一方、第二次検定は区分によって年数に違いはありますが、実務経験が必須です。
また、今回紹介しているのは新受験資格であるため、旧受験資格を確認したい方は一般財団法人建設業振興基金の公式サイトをチェックしてみてください。
受験手数料・試験地
2級建築施工管理技士の受験手数料は、以下のとおりです。
- 第一次検定:6,150円(非課税)
- 第二次検定:6,150円(非課税)
また、試験地は前期と後期でやや異なります。
| 時期 | 試験地 |
|---|---|
| 前期 | 札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄 |
| 後期 | 札幌、青森、仙台、東京、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、鹿児島、沖縄 |
ただし、会場確保の都合で試験地が近隣の都道府県になることもあります。
そのため、受験する際は事前に試験地を確認しておきましょう。
合格率
2級建築施工管理技士の合格率は、以下のとおりです。
| 年度 | 第一次検定(前期) | 第一次検定(後期) | 第二次検定 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 48.2% | 50.5% | 40.7% |
| 令和5年度 | 37.7% | 49.4% | 32% |
| 令和4年度 | 50.7% | 42.3% | 53.1% |
直近でいえば、第一次検定の合格率が50%程度、第二次検定が40%程度でした。
しかし、過去をさかのぼると合格率が30%台になる年もあります。
そのため、直近の合格率のみを鵜呑みにして油断しないよう、注意が必要です。
2級建築施工管理技士の資格を取得するメリット3選

2級建築施工管理技士の資格を取得するメリットは、以下のとおりです。
- 活躍の場が広い
- 責任のある仕事を任せられる
- 1級取得への足がかりになる
「メリットはあるの?」と疑問に思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
活躍の場が広い
実は、2級建築施工管理技士は工務店やハウスメーカー、建設会社などさまざまな場所で働けるため、活躍の場が広いというメリットがあります。
さらに、有資格者は需要が高く、企業からも貴重な人材として評価される傾向があります。
今後活躍の場を広げていきたい方は、2級の取得を検討してみてください。
責任のある仕事を任せられる
2級建築施工管理技士になると、責任のある仕事を任されやすくなります。
責任のある仕事を任されると、やりがいや達成感も大きいですし、給料や手当のアップも期待できます。
また、経験もしっかり積めるようになるので、キャリアアップや転職にも役立つでしょう。
1級取得への足がかりになる
2級建築施工管理技士の資格は、1級取得への足がかりにもなります。
いきなり1級を目指すのが悪いわけではありませんが、より専門性が増すため簡単には合格できません。
そこで、まずは2級を取得して基礎知識を蓄え、検定の雰囲気に慣れておくのもおすすめです。
いきなり1級を受けるよりも、ハードルはグッと下がるでしょう。
なお、MACでは「資格取得支援制度」を実施しております。
最大10万円の合格祝金をご用意しているので、詳細をぜひ以下のリンクでチェックしてみてください。
【2級建築施工管理技士】合格に必要な勉強時間

2級建築施工管理技士の検定に合格したいのであれば、勉強時間を100〜300時間程度確保する必要があります。
例えば、1日2時間学ぶなら50日から150日ほどかかる計算です。
ただし、これはあくまで目安であり、残業や休日出勤がある方は順調に勉強が進まない可能性もあります。
そのため、余裕を持って学習計画を立てましょう。
また、勉強する際は以下の点を意識してみてください。
- 積極的に過去問を解く
- 正解か不正解かではなく理解を重視する
- スキマ時間を有効活用する
勉強を進めるときは正解か不正解かを重視しすぎてはいけません。
これは、正確に理解していなくても正解してしまうケースがあるからです。
もちろん正解しているほうが嬉しいとは思いますが、その問題で問われていることや回答をしっかり理解できているかを意識してみてください。
これを意識するだけでも、知識の定着に大きな差がつくでしょう。
1級と2級建築施工管理技士の難易度を比較
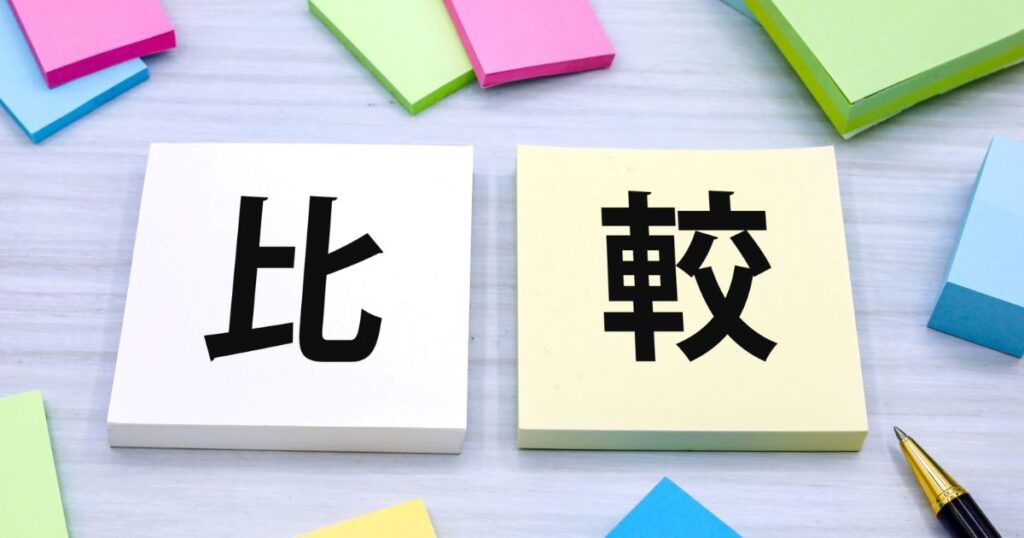
実は、直近の合格率を比較すると1級も2級もそれほど大きな違いはありません。
例えば、令和6年度の第二次検定の合格率にいたっては1級が40.8%、2級が40.7%です。
そのため、合格率だけ見ると、1級と2級の難易度はそれほど変わらないのではないかと思う方もいるかもしれません。
しかし、1級は2級よりもさらに幅広い知識や実務経験を求められます。
合格率が同程度だからといって1級と2級は同じくらいの難易度だと思っていると後悔するかもしれません。
1級のほうが求められる知識の量が多く、難易度は高いと覚えておきましょう。
1級と2級建築施工管理技士の違いとは?

1級と2級建築施工管理技士の大きな違いは、監理技術者になれるかどうかです。
1級は監理技術者になれますが、2級は主任技術者にしかなれず、小規模な工事現場の監督業務しか行えません。
また、第一次検定の受験資格や第二次検定で求められる実務経験の年数も異なります。
建築施工管理技士としてステップアップしていきたい場合は、2級取得後に1級も目指すとよいでしょう。
まずは2級建築施工管理技士を目指してみよう!

2級建築施工管理技士は国家資格の一つで、取得すると活躍の場が広がります。
さらに、責任のある仕事も任されるようになり、給料や手当のアップも期待できるでしょう。
ただし、合格のためには最低でも100〜300時間程度の勉強時間が必要です。
合格を目指す方は、スキマ時間をうまく活用したり、必要に応じて通信講座を活用したりしましょう。
また、資格取得に合わせて転職も検討しているという方は、ぜひMACにご相談ください。
当社は、建設業界の優良求人を多数取り扱っています。資格なしでも問題ない求人もありますので、勉強と並行してチェックしてみてはいかがでしょうか?