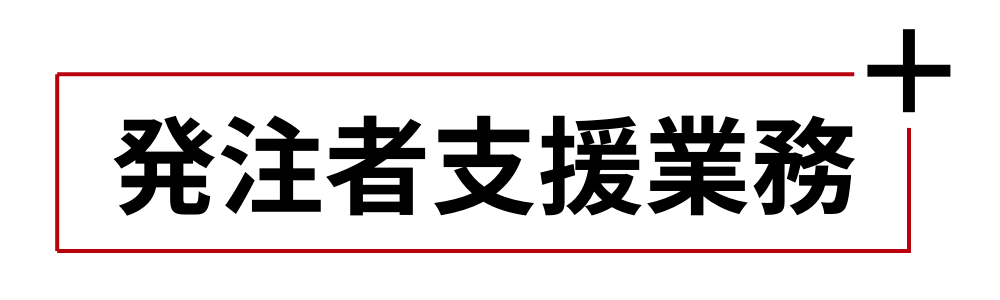社会インフラである道路や橋、ダム、鉄道など、経済活動を支え公共性の高い施設に携わっている建設コンサルタント。 今回は、建設コンサルタントに向いている人の特徴や必要な資格について解説します。
建設コンサルタントの業務内容や資格について

建設コンサルタントとは、具体的にどのような仕事内容をしているのでしょうか。 それは、社会基盤の充実の為に必要な各種公共事業の企画・調査・計画・設計・施工管理業務になります。 国土交通省のような官公庁や民間企業を顧客とし、コンサルティングを行い社会の発展に貢献する業務です。 また、特別に必要な資格は無く、未経験でも仕事に就くことができる可能性があります。 参考コラム:「建設コンサルタントは大変」ってホント?建設コンサルタントの現実と仕事の魅力を紹介
建設コンサルタントに向いている人の特徴

建設コンサルタントに向いている人の特徴とはどんな人でしょうか?
責任感が強い人
建設コンサルタントは、社会インフラにとても影響のある仕事です。また、建造物においては手抜きがあってはいけないため、リスクに対してしっかりと伝達する必要があります。 また、長い工期を安定的にこなすために、コツコツと努力を積み重ね、最後までやりきる人が適性と考えられます。
コミュニケーションスキルのある人
技術職や多くの関係するスタッフに対して指示を出し、工期や予算を管理しながら予定通り建造物を完成させるという壮大なミッションを達成させなければいけません。そのためには協力体制や関係構築を保つためのコミュニケーションスキルがとても大切になってきます。
じっくりと仕事をしたい人
建設コンサルタントは多くの工程に関わりますが、専門的で幅広い知識が求められます。建造物に関わる多くの業務を支える立場であり、その先には人々の生活の安全にも影響する重要な任務です。これらの仕事をこなすためには、じっくりと仕事に取り組む必要があります。
社会的意義のある仕事がしたい人
自然災害が多い日本では、台風や豪雨の復旧作業など人々の暮らしを守る重要な仕事になります。社会貢献としても大きな影響を与える点では、他の仕事では得られないやりがいを感じることでしょう。
地図に残る、形が残る仕事がしたい人
建設コンサルタントとして携わる建造物は、大規模のものが多いため、長い月日を経て完成した時の達成感は、他には変えられない喜びとなります。 そしてその建造物は、長期にわたり残り続けるため、それをやりがいと感じる人も多くいます。地理に関わる工事では、地図が更新されるほど影響のある仕事といえます。
建設コンサルタントの資格

前述通り、建設コンサルタントになるための特別な資格は存在しません。 コンサルタント会社に就職をし、建設コンサルタントとして働くことが一般的です。 その中で、コンサルティングの管理技術者として務めるための条件はあり、この場合は二つの資格のどちらかを保有する必要があります。
技術士(国家資格)
技術士制度は、「科学技術に関する技術的専門知識と高等の専門的応用能力及び豊富な実務経験を有し、公益を確保するため、高い技術者倫理を備えた、優れた技術者の育成」を図るための国による資格認定制度(技術士法に基づく制度)です。 科学技術に関する高度な知識と応用能力及び技術者倫理を備えている有能な技術者に技術士の資格を与え、有資格者のみに技術士の名称の使用を認めることにより、技術士に対する社会の認識と関心を高め、科学技術の発展を図ることとしています。 引用:公益社団法人日本技術師会
RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)
RCCMとは、Registered Civil Engineering Consulting Manager(シビルコンサルティングマネージャー)の略称です。建設コンサルタントなど業務の円滑かつ的確な実施に資するとともに、優秀な技術者が積極的に活用されることによって、建設コンサルタントの技術力の向上が図られることを目的に創設されています。 引用:一般社団法人建設コンサルタンツ協会/シビルコンサルティングマネージャ資格制度概要
建設コンサルタント登録制度について

建設コンサルタントになるための特別な資格は存在しないものの、前述通り技術士など建設コンサルタントに関連する資格を持つことは、当然有利です。 資格保有者を雇用すると、その会社自体が国土交通省「建設コンサルタント登録制度」に登録できます。それにより信用度がアップするのです。 つまり、国土交通省など主に公的機関からの発注者業務を受託している建設コンサルタント会社は、資格保有者が在籍しており、実績や信用度があるといっても過言ではないでしょう。
建設コンサルタント登録制度登録要件
主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。 1.登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)を置く者であること。 技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格して同法による登録を受けている技術士であることが必要です。なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。 2.財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。 (1)法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上である者 (2)個人の場合は、自己資本が1000万円以上である者 引用:国土交通省/建設コンサルタントの登録に関する情報 このように自己資本が1000万以上あれば個人でも登録ができます。
メリットの多い建設コンサルタント登録
登録する会社は、会社の信用が上がるだけではなく、公共工事の受注や入札などに参加する際には簡素化できたりと何かとメリットが多いのです。 簡素化とは、有資格者名簿の作成や入札参加資格の確認手続きのことを指し、 建設コンサルタントの登録内容として以下の情報を提出するためです。 ・業者概要(登録番号、商号又は名称、代表者名、所在地、営業所、登録部門) ・受注実績、技術的能力(直前3年間の業務経歴や事業収入金額) ・業者規模、技術者数(資格者ごとの使用人数や資格者一覧など) ・経営状況(財務に関する資料)
まとめ

今回は、建設コンサルタントに向いている人の特徴や必要な資格について解説しました。 建設コンサルタントでは、コンサルティングのための管理技術者の資格はあるものの、基本的には実務経験を重視していることが特徴といえるでしょう。 これは、建設コンサルタントに限らず、建設業に関わる資格取得では実務経験が重要とされているケースが多いといえます。 今後、建設業への就職を検討されている人は、実務経験を重視する業界であることを意識し、自分に合った仕事を探してみてはいかがでしょうか? 株式会社エムエーシーでは、発注者支援業務として、国土交通省やNEXCO、都道府県の公共事業の建設業務を全国で展開しています。 少しでも、ご興味がある方は、ぜひご検討してみてください。