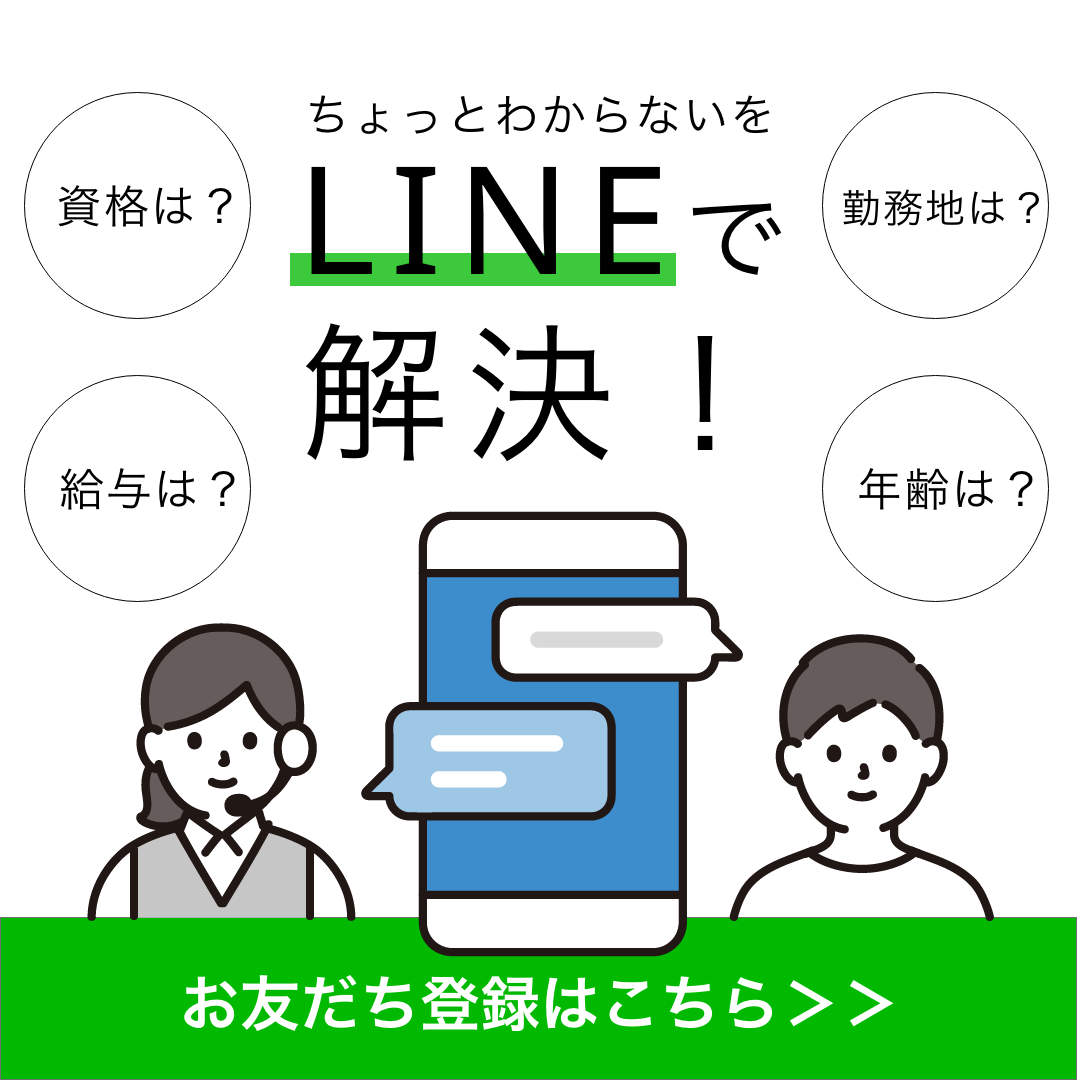建設業における残業問題とは?残業規制と働き方改革が与える影響について解説

建設業は残業時間が長く、きつい仕事というイメージがあります。
実際、他業種より労働時間が長いというデータがあり、決して楽な仕事ではありません。
しかし、2024年4月から本格的に始まった建設業の残業規制により、残業時間は今後減少すると予想されています。
単に残業が規制されただけではなく、適正な工期設定やDX化による労働者の負担減、作業効率の向上も進められています。
建設業への転職を考えている方にとっては、労働条件の改善は追い風になることでしょう。
今回の記事では、建設業における残業の現状と規制の内容、残業時間を減らすための取り組みについてご紹介します。
この記事でわかること
- 建設業の労働時間
- 建設業の残業が多い理由
- 建設業の残業を減らすための取り組み(残業規制と働き方改革)
建設業界への転職を検討している人は、以下のリンクからご相談ください。
目次
建設業の労働時間

建設業の労働時間は他業種と比べて長い傾向にあります。
以下のデータは、厚生労働省が公表した年間実労働時間の推移(全産業・建設業・製造業の3業種を比較)です。
令和3年度における建設業の年間労働時間は1,978時間で、製造業1,874時間、全産業1,632時間を上回っています。
また、平成9年度からの減少幅は48時間で、製造業98時間、全産業255時間を下回っています。
建設業は他産業より労働時間が長い上、長時間労働が慢性化した状態だといえるでしょう。
建設業の労働時間が長くなる理由

建設業の労働時間が長くなる主な理由は以下の5点です。
・人手不足
・業務の多さ
・クライアントからの無理な要望
・工期遵守の徹底
・建設業独自の体質
それぞれの理由について詳しく解説します。
人手不足
建設業の労働時間が長くなる最大の原因は人手不足です。
少子化による労働人口の低下に加え、建設業は「3K」と呼ばれるように、きつい仕事というイメージがあるため、敬遠されてしまうことも少なくありません。
人手不足により一人当たりの作業量が増えることで、労働時間が長くなってしまいます。
長時間労働を強いられる環境の中で離職者が続出し、さらに一人あたりの労働時間が増えてしまうという負の連鎖が、建設業における長時間労働の慢性化につながっています。
建設業の人手不足問題に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
業務の多さ
建設業は業務量の多い仕事です。
特に施工管理技士のような技術職は、現場での管理業務に加え、書類作成や打ち合わせなどさまざまな業務があります。
現場作業の前後に大量の業務を処理しなくてはならず、早朝から深夜まで働くことも珍しくありません。
さらに休みの日も会社やクライアントから連絡が来ることがあり、休日出勤を余儀なくされる場合もあります。
クライアントからの無理な要望
建設工事では、発注者や元請け業者といったクライアントから無理な要望を受ける場合があります。
プロジェクト開始前はもちろんのこと、施工中にも追加工事や工期の変更など、さまざまな要望が出ることもあります。
断ると次回から施工を依頼されないリスクもあるため、無理な要望でも受け入れざるをえないケースも少なくありません。
クライアントの要望通りに工事を変更するためには書類の作成や現場との調整といった対応が必要になり、残業が増えてしまいます。
工期遵守の徹底
工期が厳しいことも残業時間の増加に影響しています。
建設業は工期遵守が原則です。
工期が遅れると会社の信用がなくなり、今後の取引に悪影響が出てしまいます。
しかし、悪天候や資材の遅配、用地買収や協議の遅れなどにより工事が遅延するケースも少なくありません。
遅れを取り戻すためには夜間施工や土日祝日出勤で対応しなければならず、残業時間が増えてしまいます。
建設業独自の体質
古い価値観や慣習が残されている点も、建設業の残業時間を押し上げる要因になります。
建設業はいまだ旧時代的な体質のところも多く、「残業は当たり前」、「新人は先輩より早く出勤すべき」というように、残業を美徳とする風潮が見られる会社も少なくありません。
建設業独自の古い体質により、たとえ業務が終わっていても帰りづらい雰囲気があったり、残業削減のための取り組みが進まなかったりすることから、残業時間が増えてしまう場合もあります。
建設業における残業規制

建設業における過重労働問題は慢性化している状態です。
しかし、2024年より「働き方改革関連法」により、改正労働基準法に定められた時間外労働の上限規制が建設業に適用されたことから、今後残業時間は減少すると期待されています。
「建設業の2024年問題」とも呼ばれる新しい残業規制では、時間外労働の上限や違反時の罰則、対象外となるケースについて定められています。
以下に詳しくご紹介しましょう。
残業ルールの原則
労働基準法では、以下のように労働時間の大原則が定められています。
| 法定労働時間:1日8時間、週40時間 法定休日:毎週少なくとも1回 |
以上を超える時間外労働や休日労働をさせる場合には、労使間で36協定を結び労働基準監督署への届け出をすることが必要です。
ただし、36協定においても、時間外労働の限度時間は月45時間かつ年間360時間とされています。
しかし、36協定において「特別条項」を定めることにより、限度時間を超えて時間外労働をさせることが可能です。
特別条項を設ける場合は、適用回数や期間について明確に定め、従業員の健康管理措置などの条件を満たさなければなりません。
36協定は不利な労働条件を強いられないよう規制を設け、従業員を守るための決まりです。
今回の法改正までは、建設業は36協定の適用を除外されており上限規制が設けられていませんでした。
しかし、現在では建設業も時間外労働の規制が適用されるようになりました。
新ルールでは建設業も時間外労働に上限が設けられた
先述の通り、2024年4月以降は建設業においても時間外労働に上限が設けられるようになりました。
法改正後は罰則の規定もあり、違反者は処罰を受ける場合もあります。
たとえば、特別条項を定めた36協定を締結することなく、月45時間を超える残業をさせた場合、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されることがあります。
上限規制の適用が除外されるケース
建設事業において、災害時の復旧・復興関連工事においては規制の適用が一部除外されます。
| 適用除外 | 適用 |
| ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ・時間外労働と休日労働の合計が2〜6ヵ月で平均80時間以内 | ・時間外労働が年720時間以内 ・時間外労働が月45時間を超えられるのは年6回が限度 |
上記のルールは災害という緊急事態において、復旧対応や保守といった対策を迅速に行うことを目的としています。
建設業における残業規制については以下の記事でも詳しくご紹介していますので、あわせてお読みください。
建設業は、もっと働きやすくなる!時間外残業規制や国土交通省の取組を解説
労働時間削減のための取り組み
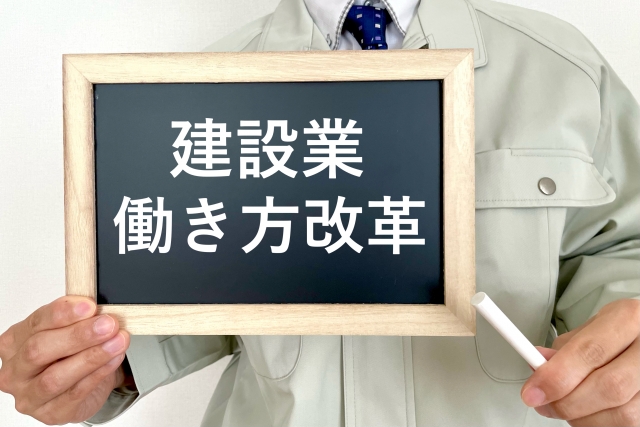
「働き方改革関連法」によって、建設業にも残業規制が適用されるようになりました。
しかし、法が整備されただけでは建設業の残業問題は改善されません。
工期厳守の風潮や人手不足により、労働時間の短縮が困難であるためです。
建設業界では、現在官民一体となって「働き方改革」に取り組んでおり、残業問題を始めとした建設業の労働問題を解決するさまざまな施策が進められています。
具体的な取り組みは以下の通りです。
適切な工期設定
先述の通り、建設業は工期遵守のために過酷な労働をせざるをえない状態です。
国土交通省は「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定し、ガイドラインに基づいた適切な工期設定を推進しています。
あわせて、適切な工期設定を過去データをもとに自動算出できる「工期設定支援システム」の公開、周知を行っています。
生産性向上のための取り組み
人手不足が慢性化している建設業において残業時間を削減するためには、業務効率化や生産性向上に取り組むことが重要です。
先述の「建設業働き方改革加速化プログラム」において、国土交通省はICT活用の推進や申請手続きの電子化を通じて生産性向上を図る取り組みを行っています。
さらに、建設リカレント教育による人材育成を推進する施策も進められています。
リカレント教育とは、学校を卒業した後で再度受ける教育のことです。
リカレント教育の推進策としては、教育訓練休暇給付金や教育訓練期間中の従業員への融資制度などがあります。
上記のような取り組みにより業務効率の改善や従業員一人ひとりのスキルアップにより生産性が向上することで、残業時間の圧縮につながる可能性があります。
建設業におけるICTの活用について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
建設DXで着目すべきポイントや国の取り組みについて解説します
技術者配置要件の合理化
建設工事では、工事の規模によって主任技術者もしくは監理技術者を配置することが義務づけられています。
しかし、人手不足が続く建設業では、技術者の確保が困難です。
条件を満たせば複数の現場を兼任することも可能ですが、技術者によって労働時間の不均衡が生じ、過重労働を引き起こしてしまう点が課題とされていました。
不均衡是正の対策として、技術者配置要件の合理化が進められています。
合理化により非専任や配置不要となる条件が緩和されることから、業務分担や勤務時間の均衡化につながると期待されています。
技術者配置要件緩和について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。
主任技術者に専任性が求められる工事の要件とは?条件や要件緩和も解説
残業への意識改革
建設業の中には、企業文化として「残業は当然」、「残業は美徳」という意識が定着している場合があります。
残業問題を解決するためには、まずマネジメント層が残業への意識を変え、従業員への周知や残業を削減するための対策を行うことが重要です。
残業への意識改革につながる国の取り組みとしては、週休2日制の推進が挙げられます。
具体的には、公共工事において週休2日制を導入した施工者への優遇措置や、週休2日制を達成した企業の積極的な評価が進められています。
建設業における働き方改革のポイントや事例を知りたい方は、以下の記事をお読みください。
2024年に建設業の働き方改革が強化!取り組みについて詳しく解説します
まとめ|建設業は今が転職のチャンス!興味のある方はMACへご相談ください

建設業の残業問題と、対策として進められている残業規制や働き方改革について解説しました。
建設業は慢性的な人手不足であり、業務量が多いことから過重労働になることも少なくありません。
しかし、残業規制や生産性向上のための取り組みにより、今後残業問題は解決の方向に向かうと期待されています。
建設業は生活に欠かせない建物やインフラに関わる仕事であり、将来性や安定性の高さが魅力です。
残業問題が改善されたら、建設業には多くの人材が流入する可能性があります。
建設業へ転職するなら、今が絶好のチャンスだといえるでしょう。
MACでは、建設業への転職を考えている皆様を徹底的にサポートします。
興味のある方は、LINEにてお気軽にご相談ください。